
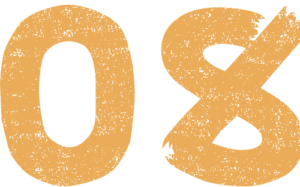
ソーシャルインクルージョンな
場所・モノ・コトをピックアップ
東京都 産業労働局雇用就業部
及び
公益財団法人東京しごと財団ソーシャルファーム支援センター
2024.10.23

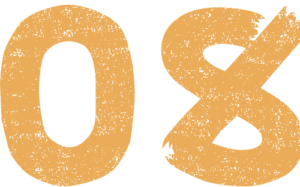
仕事を通じて、どんな人も参加できる社会へ
さまざまな理由で働きづらさを抱える人々が、他の従業員と共に働く社会的企業「ソーシャルファーム」。インクルーシブな働きかたとして、本サイトでも、働く人たちの声を度々取り上げてきました。しかし、諸外国に比べて日本ではまだまだ馴染みの薄いもの。そこで、国内で唯一、ソーシャルファームを推進するための条例を定める東京都・就労支援施策担当課長 奥鳴浩史さんと、実際に事業者の創業・経営活動をサポートするソーシャルファーム支援センターの末廣康二さん(公益財団法人東京しごと財団)を訪ね、「ソーシャルファームとは何か」「東京都が描くソーシャルファームの未来」について聞いてみました。
ソーシャルファームって何?
一般企業と同様に事業収益をあげ、かつ就労困難者たちが適切なサポートを受けながら他の従業員と一緒に働くインクルーシブな事業所、それがソーシャルファームです。さまざまな理由で就労に困難を抱える人たち「就労困難者」の社会参加を進める取り組みでもあります。
東京都が定義する「就労困難者」とは
障害者や刑務所出所者、元ひきこもりの方など、社会的、経済的、その他の事由により働くことに困難を抱える人。東京都認証ソーシャルファームでの雇用においては、都が設置する認証審査会が個別に配慮すべき実情等を確認しています。
ソーシャルファームの歴史は、1970年代、イタリアのとある精神病院の開放から始まります。当時の精神病院には、外界から隔絶され、患者の扱いに人権的な問題を抱えた施設もありました。事態を重く見たトリエステ県立精神病院の院長だったバザーリア医師は、精神病院を解体。ソーシャルファームの原型となる労働者生産協同組合(CLU)を設立し、元患者が適切なサポートのもとで働ける地域環境を整えることに尽力しました。

働きたいけれど、働けない――そんな人々を支援する取り組みは、ドイツ、イギリス、ギリシャ、フィンランドとヨーロッパを中心に拡大していき、現在でも全世界でその数は増え続けています。韓国でも2007年に社会的企業育成法が定められ、3,228ものソーシャルファーム(社会的企業)があります(2018年時点)。

東京流のソーシャルファーム。気になる認証の基準は?
2019年、東京都は日本で初めてソーシャルファームを推進するための条例「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」を公布。導入が検討され始めた大きなきっかけは、「人材問題」でした。

奥鳴さん
条例の検討を行なっていた当時は就労が困難な方が国内に約1500万人もいる一方で、東京都の有効求人倍率が2倍を超えている状況でした。雇用情勢は好転しているのにも関わらず、働きたくても働けない方がこんなにもたくさんいる。この状況をどうにかしたい、そういった想いで取り組み始めたのが「東京都認証ソーシャルファーム」です。
現在東京都では条例に基づいて、ソーシャルファームの認証を行なっています。認証には以下の基準を満たす必要があり、認証されると、最大5年間の補助金やさまざまなサポートを受けることができます。
認証基準① 自律的経営
ソーシャルファームの中で最も重要な基準のひとつが、自律的経営。ソーシャルファーム認証を受けると、その事業所は経済的自立を目指して、最大5年間、運営費に対する補助金が受け取れます。
認証基準② 就労困難者を全体の20%以上かつ3人以上雇用
ソーシャルファーム・ヨーロッパの定義では、全従業員の少なくとも30%は就労困難者であることが求められています。東京の基準は諸外国に比べるとやや少ない割合ですが、中小企業の多い東京では、職能教育や精神的ケアなどのサポートを、よりきめ細かく行き渡らせることができる人数を加味して設定されています。
認証基準③ 就労困難者と他の従業員が共に働く
ソーシャルファームでは、さまざまな人が同じ場所で働きます。新たに仲間に加わる人材との相互理解を深めながら事業活動を行ないます。事業者側が「この人と一緒に働きたい。この人をサポートするためにどんな体制が必要か」と考えることが重要です。
他にもこんな基準が……
・運営主体が法人格を有していること
・障害福祉サービスの指定を受けている事業所ではないこと など

奥鳴さん
これらの基準を元に審査し認証する上で忘れてはいけないのは、就労困難者の方に対する社内の偏見への配慮です。ソーシャルファーム認証審査会が「就労困難者」と認めることで、かえって職場の居心地の悪さにつながらないように、認証した後も丁寧に時間をかけて支援するようにしています。
ソーシャルファームを東京都と事業所が共に育てていく。
では、実際にソーシャルファームでは、どのようにして誰もが働きやすい環境を整えているのでしょうか。
ひとつは「勤務時間のフレキシブルさ」。東京都では認証するソーシャルファームに、短時間雇用やリモートワークへの切り替えなど、その人の状況に応じて柔軟に対応できる勤務体制を推奨しています。就労困難者の抱える事由はさまざまですが、多くの方に共通するのが勤務時間の問題です。自身の障害から長時間の集中ができない、通院のために平日の午前中は勤務ができない人などの、勤務時間を柔軟にすることで働けるようになる人は意外にも多い、と奥鳴さんは話します。
「ちょっと具合が悪いので今日は帰ります」などが言える雰囲気や、「働いた分はしっかりと給与が貰える」という心理的・経済的安全性が保たれた状態を職場内に作ることが大切です。
そして、もうひとつは「職場を自分の居場所だと感じられること」。朝の体調確認から始まり、仕事のスケジュールの確認や業務後の振り返りはもちろん、キャリアアップのアドバイスや人間関係の悩みまで、人によって声掛けやヒアリングする内容を変えることで、いつでも相談しやすい関係性を築いていくよう支援しています。

奥鳴さん
認証にあたって、我々は実際に事業所へ伺いますが、その一日で環境づくりの細かな点の全てができているかを判断することは難しいです。
認証後も継続的に対話をしながら、足りない部分を補っていくことを大切にしています。東京都、ソーシャルファーム支援センターと事業所とが、一緒にレベルアップを目指すことで「東京都認証ソーシャルファーム」が育っていくのだと考えています。認証の前に「予備認証」という準備期間を設けているのも、そういった考えによるものです。
「予備認証」とは
就労困難者の雇用を今後予定する事業計画で、認証基準に適合するものを予備認証という形で認証。180日の予備認証期間に要件を満たすことで、その年の正式認証を受けることのできる制度です。
現場を支える
“ソーシャルファーム支援センター”のしごと
ソーシャルファーム創設の検討段階から、立ち上げ、自律的経営を達成するまでを総合的にサポートしているのが東京都しごと財団 ソーシャルファーム支援センターです。
「支援センターの仕事は、事業者のソーシャルファームを通じて社会貢献したいという気持ちに伴走すること。ご相談をベースに、事業者それぞれの状況やニーズなどに寄り添いながら、支援を進めていきます」と話すのは、東京しごと財団企業支援部の企業支援課長 末廣康二さん。


末廣さん
ソーシャルファームの設立を検討している段階では、雇用ノウハウや認証制度についての情報を提供します。さまざまな背景を持つ事業者が相談に来るソーシャルファーム支援センターですが、多くに共通するのは、社会貢献に対する意欲が高いことです。
予備認証を含め東京都の認証を受けたソーシャルファームへは、就労に困難を抱える方の雇用を促進するために、就労支援機関とのマッチングの場を提供しています。また、状況によっては、東京しごと財団が運営する就労困難者のための相談窓口「専門サポートコーナー」をご案内することもあります。
他にも、中小企業診断士や社会保険労務士の派遣による経営面や人事労務面での助言、資金面でのサポートなども実施。ソーシャルファームは業種や規模などが異なるので、事業者ごとにサポートの形もさまざまです。
マッチングの場とは
東京しごと財団では、事業所と働きたい人をつなぐため、年2回マッチング会を開催しており、ソーシャルファームを代表する事業所や就労支援機関が事業内容や雇用実例をプレゼンテーションし、その後交流会を設けることでお互いに理解し合い、就労に困難を抱える人たちが安定した雇用・就労の機会を得られる場となるように企画しています。

社会に新たな視点を生み出す
ソーシャルファームのこれから
2020年から始まり、現在では約49の事業所が存在する「東京都認証ソーシャルファーム」。この取り組みをけん引するお2人に、これからの東京や日本におけるソーシャルファームの展望について聞いてみました。

奥鳴さん
日本で諸外国と同じように、ソーシャルファームが普及するためには、国としての法整備も欠かせません。そのためには、都が先頭に立って着実に実績を積み上げ、検討の土台を固めていくことが大切です。また、動画やワークショップで実例紹介と学びの場を提供する「TOKYO SOCIAL FIRM ACTION」なども併せて展開していくことで、東京都、そして日本全体にソーシャルファームが根付いていくことを目指しています。

末廣さん
東京都の認証ソーシャルファームが、活躍している姿を社会に周知することで、ソーシャルファームに対する理解が広まり、自分たちもやってみようかという方が増えていくと思います。そういった良い循環を作っていきたいです。
ソーシャルファームの普及は、多様な人々が社会に参加して活躍することを可能にするだけでなく、社会に“新しい解決策”を生み出します。
例えば、施設を利用する方への食事を作る職員の人材確保に課題があるグループホームに対して、配食サービスを展開しようと試みるソーシャルファームがあります。ソーシャルファームが就労困難者の方に働く場所を提供することによって、就労困難者への支援となるだけでなく、人手不足という社会課題の解決にもつながっています。
ソーシャルファームは、さまざまな人の「働くこと」への課題を解決するだけにとどまらず、地域の課題に対するひとつの処方箋にもなりそうです。

新着記事



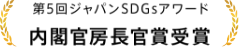









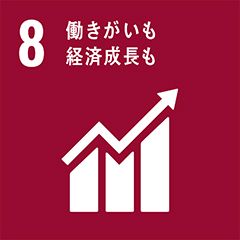













奥鳴さん
よく質問のある、従来の福祉就労とソーシャルファームの違いについてご説明します。就労継続支援(A、B型)などでは、主に障害者の就労や生産活動の機会提供や、一般就労等に向けての支援を行なっていますが、ソーシャルファームの取り組みでは、自律的な経済活動によって“就労に困難を抱える方の就労と自立”を進めることを重視します。