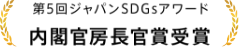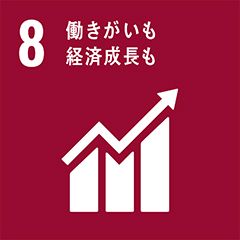貧困対策じゃない。子ども食堂をただ気軽に楽しく集える場に
普通の家で食事をふるまう
山田和夫さん(71歳)は、東京都豊島区の要町にある一軒家の自宅で独り暮らしをしている、料理が趣味のごく普通の男性です。しかし、毎月第1・第3水曜日は子ども食堂の「店主」になります。5年以上も月に2回自宅を開放し、子どもには100円で、大人には300円で手作りの夕食を提供しています。「子ども食堂って、普通は公民館やお寺、教会などを借りてやりますね。自宅でやっているのはあまり聞かないかな」と山田さんは言います。

要町あさやけ子ども食堂の始まりは、妻の和子さんが始めたパン屋「こんがりパン屋」。自宅のキッチンでパンを焼き、玄関で売っていました。加えて、池袋駅周辺のホームレスを支援するため、パンを提供する活動も行なっていました。山田さんは会社勤めをしながら、定年退職したらパン屋の仲間に入れてもらおう、と楽しみにしていたといいます。しかし、それは叶いませんでした。「60歳で会社をリタイアしたとき、老後は妻のパン屋の手伝いでもしながらのんびり暮らそうと思っていたら、突然妻に先立たれてしまいました。末期のがん。亡くなる3週間前に『ホームレス支援の分のパンを焼き続けてほしい』と頼まれ、1枚のレシピを託されてパン屋を継ぎました。2009年に何とかオープンしたけど、東日本大震災をきっかけに心が折れてしまってやめた時期もありました。落ち込んでいた時期に、妻の仲間が『山田さん、子どもの貧困問題にも取り組もう』と声をかけてくれたんです。それがきっかけで、パン屋だけでなく子ども食堂も始めました。独りじゃ何をしても楽しくなかったし、みんなでワイワイやれるからいいかなと思って」。山田さんは子ども食堂と並行して、今でも週に1回150個のパンを焼き、池袋駅周辺で生活するホームレスに無料で提供しています。
夕方は元気な声が絶えない
午後4時過ぎに自宅を伺うと、1階のキッチンではすでに10名以上のボランティアが食材の仕込みや調理に追われていました。今日のメニューは「とうもろこしご飯、ドライカレー、コーンスープ、キュウリの麹付け、焼きとうもろこし」。とうもろこしをふんだんに使っているのは、100本の寄付があったからだといいます。子どもたちはまだ1人も来ていないのに、山田家のキッチンは老若男女のボランティアのエネルギーであふれていました。

40人分の料理を作るためキッチンは大忙し

老若男女が調理に参加
午後5時半を過ぎた頃、元気な声とともに小さな子どもとそのお母さんたちが次々と食堂にやってきました。20~30代の若い母親と、小学校に上がるかどうかぐらいの子どもたちで1階にあるダイニングと和室はすぐに満席となりました。配膳が終わると、山田さんの挨拶なども特になくみんな思い思いに食べ始めます。母子で、あるいは子ども同士で楽しそうに食事をする姿がそこにはありました。食事が終わると、子どもたちは2階の部屋に行き、オモチャで遊んだりボランティアで訪れたコーラスの人たちと一緒に歌を歌ったりと自由に過ごします。母親たちも子育ての悩みごとや学校情報などを交換し合い、山田家は終始賑やかな雰囲気で満たされていました。

食事が終わっても楽しい時間は続く

食事が終わっても楽しい時間は続く
来る人が安心できる場所
多くの人が集まる子ども食堂ですが、山田さんは貧困対策で開いているつもりはないと言います。「正直、貧困対策とか福祉のことは全然考えてない。月に2回食事を提供したからといって、飢えが解消されるわけではないですから。これはただのイベント、地域の居場所づくりです。ただフラっとここにやって来ることはあり得ません。皆さん、ここで子ども食堂が開かれると知ってやって来て、家に上がったら1時間半ずっといます。食事だけなら30分で終わるのにすぐに帰らないのは、ここにいるのが楽しいからですよ」
事実、子ども食堂に来た理由を母親たちに聞くと、「毎日食事を作るのは大変だから」「ファミレスなどと違い、気兼ねなく子どもを連れて来て遊ばせられる」「ママ友といろんな話ができるから」など、まるでママ友の集まりが開かれているよう。貧困はもとより、福祉の要素さえ感じられません。
さらに山田さんは、取材の終盤に次のように言いました。「僕だったら、子ども食堂が近くにあっても行かないと思う。だって、家庭で十分だから。それでもわざわざここで1時間半を過ごすというのは、貧困であるかどうかは別にして、家庭のことで悩んでいるからだと思います。ボランティアで参加する人にも言えますよ。遠くから電車に乗って手伝いに来るのは、世のため人のためだけじゃできません。ここがその人にとっての居場所というか、活躍できる場があるから来てくれると思っています。だから僕は、自分がここで何かをしようとはあまり考えていません。ただ、居心地のいい場所や、みんなが活躍できる場所にすることだけを考えています。71歳の僕が先頭に立っていたらかっこ悪いでしょう(笑)」
現場はボランティアの参加者に任せ、裏方に徹する山田さん。メディアからの取材にも対応し、居場所を求める人に向けて子ども食堂の存在を積極的に発信しています。
徐々に広がる支援の輪
取材中も気取らない姿を見せていた山田さん。ボランティアで参加する人だけでなく遊びに来る母子も含め、山田さんの人柄があるから人は集まってくるのでしょう。取材当日も、山形から夜行バスで来た大学生や、夏休み中の近所の中学生が、子ども食堂のホームページを見て手伝いに駆け付けました。ほかにも、60冊近くの絵本を寄贈する団体や、子どもたちと一緒に歌って踊る地元のコーラス団体の人たちもおり、さまざまな形で活動を支えています。

子ども食堂をきっかけに大学で福祉を学んでいるという山形の大学生(写真左)と近所の中学生(写真右)

児童文学作家の濱野京子さん(左から2番目)や児童文学翻訳家の野坂悦子さん(左から3番目)も寄付に参加
そんな山田さんも、取り組みを始めた当初は運営が大変だったと振り返ります。運営費を工面するため魚屋でアルバイトをし、材料費に充てていたといいます。しかし、ここ1~2年で状況は大きく改善されました。テレビや雑誌に取り上げられたこともあり、活動が評価されて東京都と豊島区から運営費の援助を受けられるようになったのです。行政以外にも、民間企業からお菓子をはじめとした食料品が届けられます。取材当日も、段ボール6箱分のシリアルなどの寄付が贈られ、お土産として玄関の棚に所狭しと並べられていました。
山田さんが始めた活動は周囲を巻き込みながら広がってゆき、ボランティアだけでなく行政や企業も支援するほどに成長を遂げました。
フライング気味でも始めちゃおう
これから子ども食堂を始めようと考えている人たちに向け、山田さんからアドバイスをもらいました。
「準備万端で始めるのではなく、フライング気味でいいから始めてみることをおすすめします。小さく始めちゃって、みんなで悩みながら大きく育てていくのが一番いい。そうすれば、その人の夢を実現するための子ども食堂ではなく、みんなの夢を実現するための子ども食堂になりますから」

帰り際、子どもたちは山田さんやボランティアに向かって元気に「さようなら!」と口にします。訪れる人にとって、地域で一番気の置けない時間と空間がそこにはあります。
新着記事