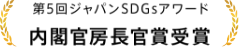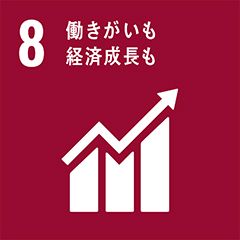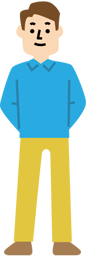

障害者と健常者の垣根をなくすには “心のバリアフリー”が大切
“バリアフリー”ってなんだ?
白くなった富士山の山頂が冬の訪れを感じさせる12月初旬、真っ青な空とさらに青く輝く海の先には江の島が見えます。ここは都心から日帰りできることでも人気の観光スポットです。
この日は、湘南バリアフリーツアーセンターのメンバー2人が、地元の飲食店にバリアフリー調査をしに訪れていました。同センターでも独自に実施していますが、今回は観光庁が実施する事業の一環で、外国人の障害者の受け入れ状態を調査するのです。車椅子ユーザーの宍戸かつ子さんは、同センターでボランティア活動を始めて3年になります。もう一人は松本彩さん、社会福祉学の専門家です。
お店の入り口は階段ですが、車椅子の人でも入れるよう、一部スロープになっています。ただ、スロープの勾配が高く、女性2人の力だけでは車椅子を押し上げきれません。
「すみませーん」
宍戸さんの声かけで、店内から店員の男性が出てきます。慣れた手つきで車椅子の脚部をつかんでスロープから引き上げて、店内まで招き入れました。一連の流れは実にスムーズで、そこに遠慮や戸惑いはありませんでした。
片方は助けが必要だと助けを求め、もう片方はそれに応じて自然と手を差し出す――。たったこれだけのことですが、そこには大きな意味があるのです。
「段差や階段があるから中に入れない、というのではなく、その段差を越える手伝いをしてもらえるかどうかを考えます。このお店の方は、そのことをよく分かっていらっしゃるから、自然と助けてくれましたし、こちらも安心です。この姿勢こそが、障害を持つ私たちにとって、何より重要なのです」(宍戸さん)
そして2人は、店内のテーブルの高さや通路の幅を巻き尺で測ったり、メニューの内容をチェックしたり、お店の人に質問をしたりして調査を進めました。この調査で集めた情報は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの前に、観光庁がホームページ上で公表するのだといいます。

調査ではテーブルの高さや通路幅などを計測

外国人向けのメニューの対応状況もチェック
「あの家族の目は社会的に死んでいる人の目でした」
湘南バリアフリーツアーセンターは、障害者とその家族が、遠出や出歩くこと気軽に楽しめるようサポートをする目的で、2016年2月に設立した特定非営利活動法人の団体です。主に、湘南エリアにある飲食店や宿泊施設などを、障害のある人たちが利用しやすいか、どういった注意点があるかなど、実際に訪れることで調査し、ホームページ上などで紹介したり、障害者が参加できるイベントを主催しています。
理事長の榊原正博さんは、同センターを設立したきっかけをこう話します。
「私はもともと医療機器の会社で設計、開発を担当していました。病気の人を助けたいという夢があって入った業界でしたが、医療機器を開発すればするほど、病気の人が増えていると感じるようになりました。
10年以上も前のことですが、自社で開発した医療機器の臨床検査のために訪れたシンガポールの病院で、いわゆる植物状態の若い男性患者のそばで付き添う母親とお姉さんの姿を見てショックを受けました。二人の表情には、喜怒哀楽というものが全くなかったのです。介護で疲れ切っていたのでしょう。彼らを見たとき、『この二人こそ、呼吸はしているものの、社会的に死んでしまっているではないか』と衝撃だったのです」

湘南バリアフリーツアーセンター理事長・榊原正博さん
その後、社会福祉の先進国であるスウェーデンを訪れ、リハビリテーションの現場を見て再び驚いたといいます。
「対照的でした。スウェーデンでは、身体さえ動かせればよいという考え方ではなく、障害者も生き生きと生きるのが当たり前。周囲も自然に手を貸しますし、障害のある人たちも自然に助けを求め、自立した生活を送っていたのです」
シンガポールで見た、社会のサポートを得られず不自由の中での疲弊した一家の姿は、榊原さんの中で、日本での病人のいる家庭や、障害者の状況と重なりました。
「人の幸せ、人の喜びってなんなのだろう」と考えた榊原さんは、「障害者でも病人でも笑顔になることが大切では」と思い始めます。旅行に関することが笑顔につながりやすそうだと、湘南バリアフリーツアーセンターの設立を思い立ちました。高校の先輩や地元のつながりで、協力者は次々と現れました。みんな本当は何か手伝いたいのだということが伝わってきました。
最初に行なったのは、「バリアフリービーチ」でした。車椅子の人たちと一緒に材木座海岸で泳ぐという活動です。障害者1人につき、健常者2人、医療関係者1人がついて、海で泳ぐのですが、海遊びの得意な健常者は医療にも障害者の対応の仕方にも明るくない、医療関係者は海のことを知らないなど、それぞれの得意不得意がうまく混ざって、全員にとってウィンウィンになる楽しいイベントとなり、その後恒例化しています。

砂浜にマットを敷いて通路を作り、水上車椅子で海の中へ!
見えてきた“手ごたえ”
「『バリアフリービーチ』を続けているうちに、隣町の由比ヶ浜のビーチがバリアフリーになりました。由比ヶ浜の海の家の運営をしている人が、我々のビーチイベントを見て、バリアフリーを実現してくれたのです。嬉しかったですね」
スロープを付けて段差を少なくする、案内板を点字でも表示するなどといったことは、ハード面での対応ですが、実は、それ以上に大切なのはソフト面です。やはり人はどのように対応されるかによって心象が大きく変わります。相手が自然に手を差し出してくれると、受け手も自然にその手を取りたくなるという心理が働くのです。バリアフリーが実現できるか否かは、ここにあるのではと榊原さんは考えています。

「“心のバリアフリー”こそが大事」(榊原さん)
「日本人は内気なところがあり、障害者は助けを求めたくても『無理なんじゃないか』『理解してもらえないんじゃないか』という不安を感じ、健常者は助けたくても『どう声をかけたらいいのか、どう手を差し伸べたらいいのか分からない』という壁があります。実は、この双方の気持ちこそが、“バリア”になってしまっているのです」
さらに、かける言葉も間違えやすいそうです。
「多くの人は『大丈夫ですか?』と聞きます。でも、そう聞かれるとつい、『はい、大丈夫です』と答えてしまうのです。答えた後に『本当は困っていたのに』と後悔しても、もう遅いんですね。でも、『お困りですか?』とか『お手伝いしましょうか?』と声をかけていただくと、当事者も『はい、お願いします』とすんなり応えやすくなります」
声のかけ方ひとつで、そんな違いが!と驚きますが、こんなことでも知っているのと知らないのとでは大きな違いだそう。
「両者の間に横たわるのは『知らない』ことだと思うのです。健常者は手の差し伸べ方を『知らない』し、障害者も手の借り方を『知らない』。だったら、両者が互いを知れるよう、私たちが橋渡しをできたらなと思うのです」

「当事者も地域の中に入って発信し、役割を持つと、もっと地域が変わると思う」(松本さん)
2020年東京オリンピック・パラリンピックを追い風に
この日、お話しを聞かせてもらった場所は、海に面した眺めのいいカフェ『SUNCAFE PARADISE』。ここも数年前までは車椅子用のスロープがありませんでしたが、オーナーの理解で、入り口にスロープができ、店内も車椅子で自由に行き来できるようになっています。このように、活動をしていく中で、理解者や協力者は着々と増えています。
同センターが活動をしていて発見したことは他にもあります。観光地として人気の高い鎌倉は、坂の多い町であるため、階段や石畳が多く、障害者にとっては長年、敷居の高い場所でした。ところが、実は地元の人たちは協力的だということが分かりました。2016年には地元の着物レンタルショップの協力で、着物を着て鎌倉観光を楽しむイベントが実現しました。今では恒例の行事となっています。

障害の有無にかかわらず、着物を着て桜が見頃の鎌倉巡りを楽しむ

「皆さんが何か手助けをしたいと思っていると分かると、私たちも勇気が出ます」(宍戸さん)
特にオリンピックイヤーとなる2020年は、ひとつの節目の年になってほしいと榊原さんは願っています。
「江の島にあるヨットハーバーがセーリング競技の会場となります。湘南地域に海外からも多くの障害者の方が訪れると思います。彼らは自立しているので、外出、移動を自由にするでしょう。日本の障害者の皆さんも、そういう姿を見て、“できない”と諦めるのではなく、“できるんだ”という刺激を、彼らから受ける機会があればと期待しています」
バリアとは、実は人の心の中にあるもの。一人ひとりの“心のバリアフリー”を目指し、障害者がやりたいことをできるための支援の活動を、これからも続けていきます。
新着記事