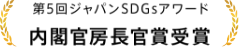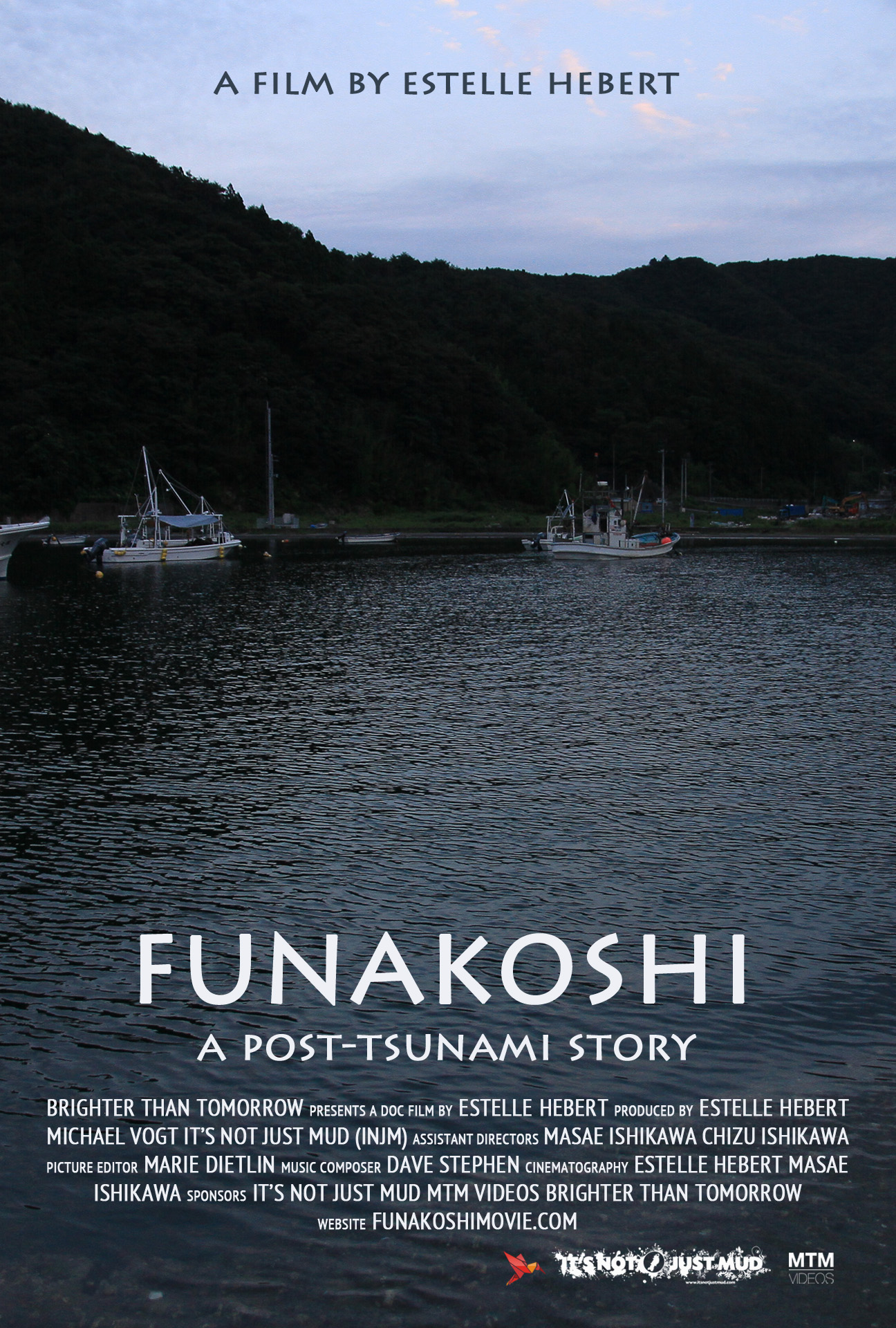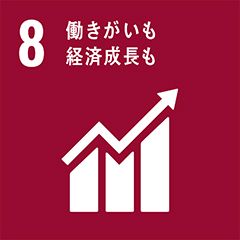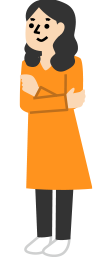
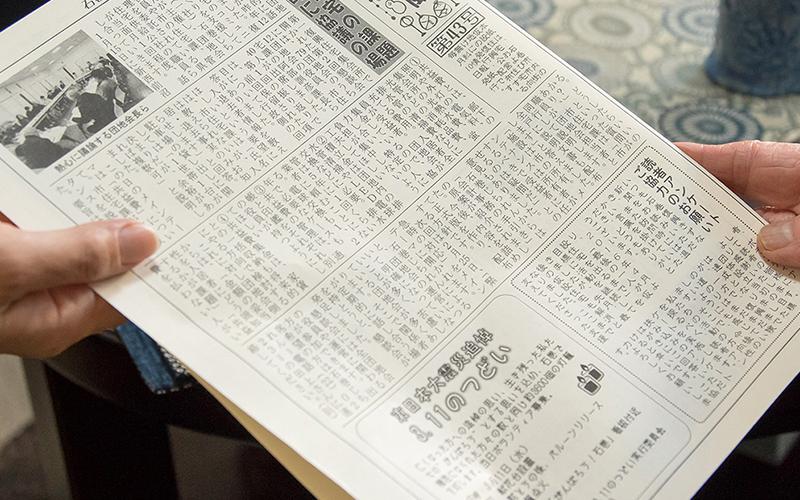
「最後の一人が仮設住宅を出るまで」被災地に新聞届ける
満開の桜の向こうにがれきが広がる石巻
「ボランティアとも石巻とも新聞とも無縁でした」と言う横浜市出身の岩元さんが、ピースボート災害ボランティアセンター(PBV)のボランティアとして、宮城県石巻市を訪れたのは2011年4月23日。雨で活動ができず、市内を一望できる桜の名所・日和山に登ると、満開の桜の向こうにがれきの山が広がっていました。岩元さんにとっての石巻の原風景です。
その後、断続的に通って泥かきなどの活動を行ない、石巻の夏の風物詩「川開き祭り」を一区切りと考え、いったんはこの地を離れました。しかし、3週間後には戻ってきてしまいます。石巻のある人が岩元さんとの出会いを喜び、「震災があったからこそ出会えた」と言ってくれたことが心に刻まれていたのです。1mmでも復興を進めたい――「ありがとう」と言われることに引け目を感じ、地元の人と距離を取ってきた岩元さんでしたが、それからは、石巻で生活しながら人と関わるようになります。


かつて民家や商店が立ち並んでいた風景は大きく変化している
無料の情報紙を仮設住宅一軒一軒に手渡し
2011年10月、PBVは仮設住宅の人々に向けて、無料の情報紙「仮設きずな新聞」を創刊。引きこもりや孤独死などを防ぐ見守り活動のため、一軒一軒に手渡しました。「石巻復興きずな新聞」の前身です。岩元さんはその年の12月から関わり、翌年7月には編集長に就任。行政からのお知らせや仮設住宅の不便を解消するアイデアなど、配布時に寄せられる声も反映しながら企画・制作しました。

A4版4ページで約6000部発行。64団地を自転車で回って配布した
岩元さんの初取材は、2012年1月に披露された雄勝町伝統の獅子舞「獅子振り」。すべてを津波で流された町民たちが、寄贈された太鼓と笛を鳴らし、借りた獅子頭とバラバラの衣装で勇壮に舞う。その心意気を「伝えたい」と強く思ったことが、新聞作りの原点となりました。
3・11から1年後の追悼行事の告知の扱いは議論になりました。岩元さんは「その日の過ごし方に苦しむ人への提案になる」と情報の掲載を主張しつつ、「思い出させてしまう」との反対意見もくみ、折り込みの形にしました。手渡す際、入れるか否か判断できるようにしたのです。
当日、岩元さんがある追悼行事を取材した際、折り込みを持つ女性を見かけました。思わず声をかけ、祈る場所を探していたとの話を聞き、「一つの情報で未来が変わる」と感じたそうです。

取材時の録音を何度も聴き直すうち突然、意味が分かるようになったという
お茶などを飲んで話をする「お茶っこ」に招かれ、コーヒーのお供に漬物を食べたり。突然ホヤをもらったり、「脳みそが凍る感じ」の厳冬を体験したり。石巻生活にはなじみましたが、新聞は資金と人手の不足により、2013年3月に休刊を余儀なくされました。アンケートでは継続を望む声が圧倒的に多く、「仮設を見捨てるのか」と住民に怒鳴られたりもしました。岩元さんは「自分の力不足」と精神的に追い込まれ、倒れてしまいます。1週間考えて継続を決め、「何も覚えてない」ほど準備に奔走し、6月に復刊。区域を広げ、石巻全域約130カ所の仮設団地に配ると、初めて見た人が「こんなのが欲しかった」と言ってくれました。
支援活動のデザインと継続性が評価される
2016年3月、PBVの石巻での活動終了に伴い、新聞の終刊が決まりました。すると、今度はボランティアのスタッフから「続けたい」との声が次々と上がります。新聞を拒絶する人やアルコール依存の人など、いろんな人に出会うこともあり一筋縄ではいかない大変な活動ですが、本当に続けたい? 面談で真意を尋ねると、それぞれにやりがいを見いだしていました。
個々の希望をかなえ、誰も犠牲にせずに続けるにはどうすればよいだろう。考えを重ねた結果、出した答えは新たに団体を立ち上げること。「最後の一人が仮設住宅を出るまで」発行すると決意し、同年6月には「石巻復興きずな新聞」創刊を果たしました。
配布先は主に仮設住宅から復興住宅(災害公営住宅)になりましたが、ロゴ入りビブスを付けて「きずな新聞お届けに来ました!」と、一軒一軒に手渡すスタイルは変わりません。2018年にはその「支援活動のデザイン」と継続性が評価され、グッドデザイン賞を受賞しました。2020年3月現在、約5000部を月に1回発行。高齢者からの要望を受けて、希望者に渡すA3の拡大版も好評です。

新聞配布に同行させてもらったのは2020年2月。1日かけて湊町復興住宅3棟、78世帯に配るスケジュールで、この日のボランティアは4人。2人組に分かれ、進捗状況をLINEで共有しながら、同じ棟を上階からと1階から回り、行き合ったら終了です。
8カ月の長男を抱っこした岩元さんが顔を出すと、人々の表情が明るくなります。岩元さんはお茶っこで近況報告やイベントの相談、震災にまつわることなど、授乳も交え、住民とざっくばらんに話します。「〇〇さん、出てるよ」と新聞の内容も紹介。身近な人の記事は興味を引き、励みになるようです。「新聞は住民さんの見守りに必要なツールなんです」と岩元さん。

稲井範子(いない・のりこ)さん宅のお茶っこにおじゃまさせてもらった

新聞配布の活動後は、事務所に戻って一人ひとり報告書をまとめ、「振り返りの会」を行ないます。住民の体調の変化などの報告をはじめ、「玄関先でドアを開けたまま話していて『寒くないですか』と言ったことが『話を切り上げたい』と受け取られたかも」といった気づきも共有され話し合われました。

季節の手紙のように、住民さんに届ける
2020年1月、仮設住宅の最後の住民が退去し、きずな新聞は「最後の一人が仮設住宅を出るまで発行する」目標を達成。最大1万6788人が暮らし、7153戸整備された石巻のプレハブ仮設は役目を終えました。食べ物、泥かき、住む所など、必要な支援が明確だった震災直後と比べ、今は百人百様の困りごとに対し、支援も一筋縄ではいきません。9年前、震災一色のテレビを見て「被災地の役に立ちたい」と熱く思った岩元さんも年を重ねました。現在は新聞舎の運営が主な仕事となり、結婚・出産を経て、生活の軸足は東京にあります。今後はどうするのでしょうか。
復興住宅の課題の一つはコミュニティ作りです。人々の距離感が否応なしに近かった仮設住宅から復興住宅に移ると、引きこもりがちになり、人間関係が作れない人も出てきます。集合団地に初めて住む人には理解しにくい「共益費」問題もあります。きずな新聞では、こうした問題の解決を目指す情報や取り組みを紹介。また、「何で自分がこんな目に」と思い悩む人に向けて、考え方を変えるきっかけになるよう、被災者、がん患者、LGBTなどマイノリティの声を取り上げる企画も始めました。
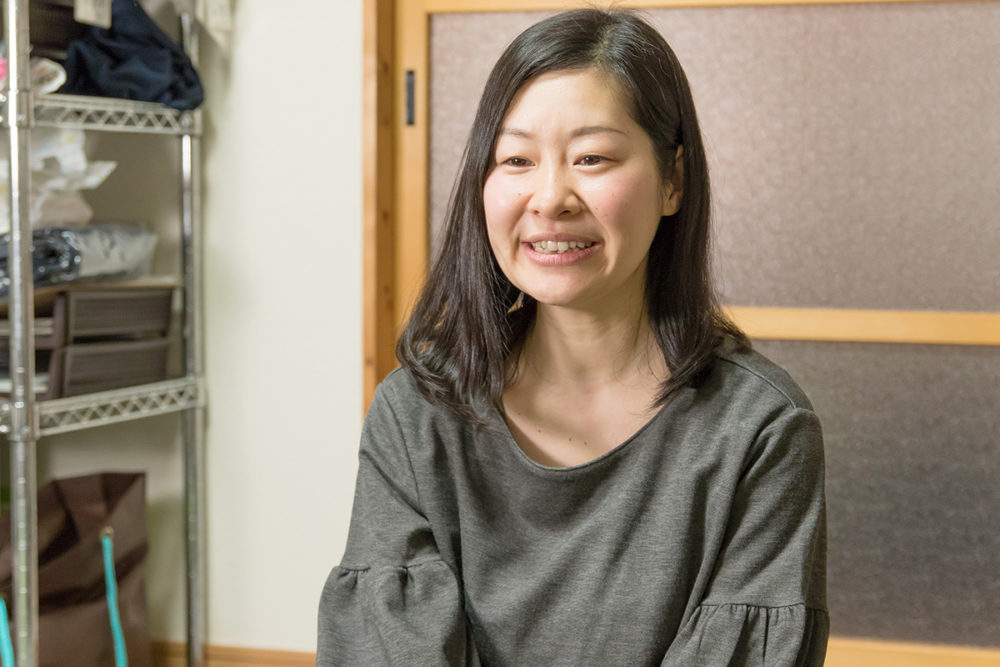
岩元さんは今も、よそ者として各地の情報を伝える「風の人」の視点を大切にしている
「ずっと続けてきたあきちゃんだから、ついていくんだよ」と地元の人が惜しまず協力し、支えてきたきずな新聞。
これまで年間200人のボランティアを受け入れてきましたが、4月からはある程度メンバーを固定した新体制で、年4回の発行になります。身近な人や出来事を伝えてきた新聞は今後、内容をより充実させ、季節の便りとして届けられます。一人ひとりに寄り添うような記事に、これからも多くの「住民さん」が励まされるに違いありません。新聞のかたちがどのように変化していこうとも、岩元さんは一生、石巻と関わるつもりでいます。

製作:心の復興映画製作委員会 http://lifegoeson-movie.com/
DVD ¥3,800円+税 発売元:TBSサービス 販売元:TCエンタテインメント
東日本大震災から6年後、岩手・宮城・福島各地で新しい一歩を踏み出そうとしている人々を、自然豊かな風景とともに映し出したドキュメンタリー映画。

新着記事