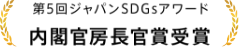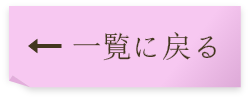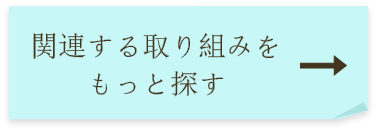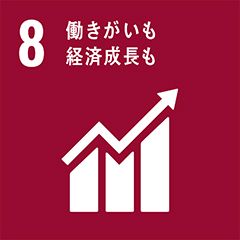【ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health/国際生活機能分類)】
あいしーえふ(こくさいせいかつきのうぶんるい)
人間の生活機能と障害の分類法のこと。1980年に発表された「WHO国際障害分類(ICIDH)」の改訂版として、2001年にWHO(世界保健機関)総会で採択され、世界で活用されている枠組みです。
①健康状態
②生活機能(心身機能・身体構造/日常生活に必要な動作や余暇などの活動/社会などへの参加)
③背景因子(その人をとりまく環境因子/価値観や嗜好など固有の特徴を指す個人因子)
上記の3つの構成要素に分類される約1500パターンの項目にあてはめ、機能や活動状態を示す評価点を加えて、本人の生活機能と障害の全体像を把握しようとするものです。障害者に限らず、すべての人に活用される分類法で、生活に関する状況を包括的に示し、今できることと障害の両方に焦点を当てることが特徴です。特に介護や障害者支援の現場では、ケアにあたる関係者同士でその人の状況を共有したり、最適な福祉サービスの提供のために活用されています。
参考サイト
「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について(厚生労働省)
ICFの活用-“「生きることの全体像」についての「共通言語」”として(厚生労働省)
事例