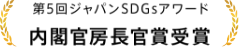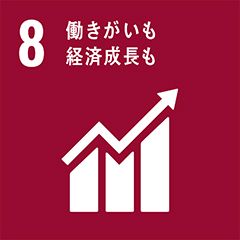“住まいの課題”に特養が取り組む理由。
高寿園と吹田市居住支援協議会の挑戦
大阪府済生会吹田特別養護老人ホーム「高寿園」は、全国の済生会施設のなかでもいち早く2023年に指定を受け、「居宅支援法人 高寿園」として支援を行なっています。なぜ、特養が地域の住まいに関する支援事業を始めたのでしょうか。その理由を担当者の皆さんに伺いました。
特養が住まいの支援を始めた理由
大阪府北部にある吹田市。住宅街の一角に立つ大阪府済生会吹田特別養護老人ホーム「高寿園」は、「一人ひとりを大切にし、やすらぎのある暮らしをささえる」をモットーに、30年以上にわたり特養やショートステイ、居宅介護支援、訪問介護、障害福祉サービスといった、さまざまな福祉事業を行なってきました。

2023年からは大阪府から居住支援法人の指定を受託。不動産団体や行政、居宅支援事業法人などが連携し、住まいの支援を行なう吹田市居住支援協議会に参加し始めました。長年高齢者福祉に携わってきた同施設が居住支援に取り組むようになった経緯を、園長の池田惠津子さんは次のように語ります。
 池田園長: 『施設でも、在宅でも「その人らしい生活」を支え、見守り、ともに育み合うこと』というコンセプトのもと、高寿園は今までも地域課題の解決や地域連携に関わる活動に進んで取り組んできました。ですから、住まいでお困りの方をサポートしようと考えることは自然な流れでした。「吹田市居住支援協議会」に参画させていただいてからは、他の参加団体の方々とそれぞれの専門的知見を交えながら居住について日々学び合っています。
池田園長: 『施設でも、在宅でも「その人らしい生活」を支え、見守り、ともに育み合うこと』というコンセプトのもと、高寿園は今までも地域課題の解決や地域連携に関わる活動に進んで取り組んできました。ですから、住まいでお困りの方をサポートしようと考えることは自然な流れでした。「吹田市居住支援協議会」に参画させていただいてからは、他の参加団体の方々とそれぞれの専門的知見を交えながら居住について日々学び合っています。
池田園長は、これまで済生会吹田病院の副院長兼看護部長を経て、2019年に高寿園の園長に就任。社会福祉法人として地域にどのような社会貢献ができるか模索を続けていたところ、居住支援事業の存在を知ったそうです。

 池田園長:大阪府が主催する居住支援に関するセミナーに参加して、改めて私たちの生活にとって「住まい」がとても重要な存在なのだと再認識しました。地域で困りごとを抱える人を支えるのが、私たち済生会の使命。2018年から吹田市から受託して当園が運営している地域包括支援センターでの経験やそこで得た地域の高齢者とのネットワークなどを活かした“高寿園だからこそできる支援”があるのではないかと考えたんです。
池田園長:大阪府が主催する居住支援に関するセミナーに参加して、改めて私たちの生活にとって「住まい」がとても重要な存在なのだと再認識しました。地域で困りごとを抱える人を支えるのが、私たち済生会の使命。2018年から吹田市から受託して当園が運営している地域包括支援センターでの経験やそこで得た地域の高齢者とのネットワークなどを活かした“高寿園だからこそできる支援”があるのではないかと考えたんです。
池田園長と同セミナーを受講した高寿園統括マネージャーの小川俊彦さんは、居住支援に携わることになった時の思いを、地域への支援がストップしてしまった当時のコロナ禍の状況を踏まえ、次のように振り返ります。

 小川さん: 吹田市には、生活困窮の問題を抱える方をサポートするためのレスキュー事業「吹田しあわせネットワーク」という独自の仕組みがあり、市内にある110の施設が加入しています。
小川さん: 吹田市には、生活困窮の問題を抱える方をサポートするためのレスキュー事業「吹田しあわせネットワーク」という独自の仕組みがあり、市内にある110の施設が加入しています。
2013年から高寿園も参加しているのですが、そこでも住まい探しが困難な方の、転居時の荷造りや荷物の搬入、生活用品の確保、生活家電の確保、生活費の捻出といった住まいの問題に対して、各施設のコミュニティソーシャルワーカーが食品・衣類・白物家電等の提供や経済的援助(社会貢献基金の活用)をするなど、伴走型の支援を行なってきました。しかし、コロナ禍で感染対策の側面から、対面での支援が難しくなったことや定例会議等が中止となり情報の共有が困難になったことで、そうした支援活動のほとんどが動かなくなってしまい、私自身、生活に困難を抱えている地域の方々への支援に携われないもどかしさを感じていました。そんな中、池田園長から居住支援事業のお話を伺い、「絶対にやりたいです」と真っ先にお伝えしたことを今でも鮮明に覚えています。
居住支援事業を始めるためには、大阪府の指定を受ける必要があります。池田園長と小川さんがセミナーを受講したのが2022年12月。申請は年に1回、同年度中に指定を受けるために残された期間は、わずか2カ月程度でした。この機を逃すと支援開始が来年まで持ち越しになってしまうため、池田園長も小川さんも急ピッチで申請業務を行なったといいます。
2023年5月には、既に発足していた吹田市居住支援協議会にオブザーバーとして参加。「居宅支援事業法人 高寿園」として正式に指定された2023年7月から、高寿園は相談業務に携わることとなりました。
多業種連携で住宅確保要配慮者の住まい探しに取り組む
高寿園も参加する吹田市居住支援協議会は、住宅確保要配慮者が安心して住宅を見つけられるような仕組みづくりを目的に2023年2月に発足。居住支援団体や不動産関係団体、吹田市の福祉部局及び住宅部局が参加し、協働で情報共有を行ないながら、住宅確保要配慮者に対して住まい探しのお手伝いをはじめ、入居後の状況確認、時には契約時の保証人になるなど、必要な支援を実施しています。
吹田市居住支援協議会の事務局を担当するのが、吹田市住宅政策室と社会福祉法人みなと寮。社会福祉法人みなと寮は、吹田市や大阪市を中心に、4つの救護施設(生活保護法に基づき障害者や生活困窮者を対象に生活全般の支援を行なう施設)、3つの特別養老人ホーム、認知症対応グループホーム、地域在宅サービスステーション、地域包括支援センターなどを運営する社会福祉法人です。事務局の大西睦高(のぶたか)さんに、吹田市の住宅確保要配慮者に関する現状を伺いました。

 大西さん: 吹田市は、府内でも極めて高い人気エリアです。そのため、賃貸物件の家賃設定も自然と高騰してしまい、低所得の方が家賃を支払うことができなくなるというケースが見られます。
大西さん: 吹田市は、府内でも極めて高い人気エリアです。そのため、賃貸物件の家賃設定も自然と高騰してしまい、低所得の方が家賃を支払うことができなくなるというケースが見られます。
吹田市居住支援協議会がこれまでに受けた相談件数は、延べ111件(2024年11月現在)。大西さんによると、他市では、外国人や刑務所出所者の相談が多いそうですが、吹田市では、DV被害を受けている人や入居中の物件の建替えにより立ち退きを余儀なくされた高齢者、精神疾患を抱えた人からの相談を受けるケースが多いと話します。
 大西さん: 私たち事務局は住まいでお困りの方に対して円滑な支援をご提供できるように、担当する居住支援法人の選定や定期的な連絡会の設定など、支援協力団体同士の調整役を担っています。新しい住まいが見つかったら支援が終わりというのではなく、移転先でも安心して生活ができるように支えていくことも私たちに求められていることだと感じています。
大西さん: 私たち事務局は住まいでお困りの方に対して円滑な支援をご提供できるように、担当する居住支援法人の選定や定期的な連絡会の設定など、支援協力団体同士の調整役を担っています。新しい住まいが見つかったら支援が終わりというのではなく、移転先でも安心して生活ができるように支えていくことも私たちに求められていることだと感じています。
もちろん、住宅確保要配慮者が生活するための住まい探しも居住支援協議会の重要な役割です。住宅確保要配慮者にはさまざまな方がいますが、例えば、ひとくちに「障害者」といっても、一人ひとり異なる特性を持っています。しかしながら、管理会社さんや大家さんは、障害のある方の入居には漠然とした不安を抱かれることがほとんどだといいます。
そんな住まい探しの問題を解決するため、大家さんへの説明や仲介を行なってくれるのが、大阪府宅地建物取引業協会北大阪支部とその協力不動産会社、公益社団法人全日本不動産協会などです。協力不動産会社のひとつであるベルクリエイト株式会社の代表取締役を務める滝井裕介さんと山﨑将吾さんにもお話を伺いました。ふたりは共に介護福祉業界での勤務経験を持ち、「福祉の不動産屋さん」という屋号を掲げて事業を展開しています。

 滝井さん:私たちは不動産業界では珍しい介護福祉士やSHP高齢者ホームプランナーなどの資格を持っています。そういった福祉業界での知識・経験を生かして、その方が抱えている問題の特性を管理会社や大家さんに正確にお伝えするとともに、入居に際して可能な限りのサポートを行なうことをしっかりとお話しします。コミュニケーションを密に行ない信頼関係を得ることが、管理会社さんや大家さんのご理解や安心につながるとても大切なポイントだと考えています。
滝井さん:私たちは不動産業界では珍しい介護福祉士やSHP高齢者ホームプランナーなどの資格を持っています。そういった福祉業界での知識・経験を生かして、その方が抱えている問題の特性を管理会社や大家さんに正確にお伝えするとともに、入居に際して可能な限りのサポートを行なうことをしっかりとお話しします。コミュニケーションを密に行ない信頼関係を得ることが、管理会社さんや大家さんのご理解や安心につながるとても大切なポイントだと考えています。
 山﨑さん: 住宅確保要配慮者の方を受け入れる管理会社さんや大家さんが、家賃の不払いや物件での事故のリスクなど、賃貸しに不安を感じておられるのは事実です。だからこそ、入居後のフォローをするのも私たちの役割。相談事があればすぐに駆けつけ、適切なアドバイスや支援を行なうようにしています。
山﨑さん: 住宅確保要配慮者の方を受け入れる管理会社さんや大家さんが、家賃の不払いや物件での事故のリスクなど、賃貸しに不安を感じておられるのは事実です。だからこそ、入居後のフォローをするのも私たちの役割。相談事があればすぐに駆けつけ、適切なアドバイスや支援を行なうようにしています。
吹田市居住支援協議会の支援
~相談開始から入居後までの流れ~
相談
吹田市都市計画部住宅政策室/吹田市居住支援協議会 主に行政や協議会の窓口に相談のあった住宅確保要配慮者から、住まいに関する希望や困りごとなどを聞き取り、協議会内で情報を共有。事務局が中心となって、担当する居住支援法人に住宅確保要配慮者に関する情報を提供する。
希望物件の調査
居住支援法人 住宅確保要配慮者本人からさらに詳しくヒアリング。不動産関係団体にメールで一斉送信し、希望に叶う賃貸物件がないか確認する。
物件の内覧/賃貸交渉
不動産関係団体 本人の希望に沿う物件があれば内覧を実施。不動産関係団体の担当者も同行し、賃貸人(家主・管理会社)に、プライバシーの保護を守りつつ賃貸の仲介を行なう。
アフターフォロー
居住支援法人/連携先となる関係機関など 「吹田しあわせネットワーク」と連携し生活に欠かせない家具や家電などを提供。入居後の安否確認や困りごとのヒアリングなどアフターフォローを実施する。

済生会だからこそできる居住支援とは
居住支援法人 高寿園は、主に高齢者や障害者の住宅確保要配慮者に対する相談業務を担当。しかしながら「若い世代の相談業務に携わることも多い」と、小川さんは話します。

 小川さん: 居住支援事業を始めた時には、高齢者の方々の相談業務を行なうものだとイメージしていました。独居で身寄りも保証人もいない、そういった方々を支えるのが特養を運営する私たちの役割だと。でも、実際に相談業務に就くと、特に若年層の方の相談を受けることが多いことに驚きました。初めて入居に至ったケースは、精神疾患を抱える20代女性の方でした。協議会の事務局から担当を任せていただき、ヒアリングを通して希望に叶う物件を扱っている不動産関係団体へと繋ぎました。
小川さん: 居住支援事業を始めた時には、高齢者の方々の相談業務を行なうものだとイメージしていました。独居で身寄りも保証人もいない、そういった方々を支えるのが特養を運営する私たちの役割だと。でも、実際に相談業務に就くと、特に若年層の方の相談を受けることが多いことに驚きました。初めて入居に至ったケースは、精神疾患を抱える20代女性の方でした。協議会の事務局から担当を任せていただき、ヒアリングを通して希望に叶う物件を扱っている不動産関係団体へと繋ぎました。
住まいの問題は、生活困窮や家庭環境など、さまざまな課題を内包しています。小川さんも、生活保護の申請業務など、これまで未知だった知識を学びながら、相談業務を行なっているそうです。
また、住む場所が決まってからのアフターフォローも、居住支援法人の大切な役割です。住宅確保要配慮者の方が安心して生活できるまでのサポートとして、吹田しあわせネットワークと連携した家具や家電などの提供や、定期的な安否確認、状況に応じた自宅訪問などを実施しています。
 小川さん: 居住支援を経て、初めて入居に至った方々にアフターフォローとして現状確認のお電話させていただく際などは、今まで接点のなかった年代の方への支援ができているなと実感します。ただ、現在当園で居住支援を担当しているのが男性スタッフしかおりませんので、お宅への訪問などを控えさせていただくこともあり、男女スタッフ体制が整えられると、今後支援の幅も広がるのではないかと考えています。
小川さん: 居住支援を経て、初めて入居に至った方々にアフターフォローとして現状確認のお電話させていただく際などは、今まで接点のなかった年代の方への支援ができているなと実感します。ただ、現在当園で居住支援を担当しているのが男性スタッフしかおりませんので、お宅への訪問などを控えさせていただくこともあり、男女スタッフ体制が整えられると、今後支援の幅も広がるのではないかと考えています。
そこで、居住支援をはじめ高寿園の事務全般を担当していた結城千恵子さんも、居住支援に関するセミナーを受講するなど、将来的には相談業務を担えるよう、日々勉強中とのこと。
 結城さん: 池田園長は常々「済生会の一員としてソーシャルインクルージョンをどのように広めていくか」と考えておられます。不動産と福祉、異なる分野が協働して、住まいにお困りの方に寄り添って活動することは、済生会の一員として責任を持って取り組まないといけない事業だと感じています。
結城さん: 池田園長は常々「済生会の一員としてソーシャルインクルージョンをどのように広めていくか」と考えておられます。不動産と福祉、異なる分野が協働して、住まいにお困りの方に寄り添って活動することは、済生会の一員として責任を持って取り組まないといけない事業だと感じています。

「特養」を住まいの選択肢にできることが高寿園の強み
高寿園が居住支援法人となった2023年度の相談件数は4件(相談のみ3件、入居成立・入居後支援中1件)。2024年度は、12月末現在で5件(相談のみ3件、支援中1件、入居成立・入居後支援中1件)。一見すると少ないように見えますが、これは吹田市居住支援協議会への相談を居住支援法人ごとに振り分けているため。今後、この制度の認知度が高まるにつれ、より相談件数は増えると予測されます。
「協議会の中で協働して、お互いが何でも言える関係性を構築するためにも、実践を促進することが大切」と話す池田園長。「済生会らしさ」「高寿園らしさ」を活かした支援にも力を入れたいと強調します。

 池田園長: ご相談の中には、独り暮らしの高齢者の方もいらっしゃいます。もしその方が認知症を患っていると判明した場合、特養への入所も選択肢としてご提示できるのが当園の強み。地域の高齢者の方が安心できる生活を支えるのが、済生会らしさであり、高寿園らしさではないでしょうか。
池田園長: ご相談の中には、独り暮らしの高齢者の方もいらっしゃいます。もしその方が認知症を患っていると判明した場合、特養への入所も選択肢としてご提示できるのが当園の強み。地域の高齢者の方が安心できる生活を支えるのが、済生会らしさであり、高寿園らしさではないでしょうか。

実際に2024年度には、介護サービスを始め市内の高齢者支援を担当している吹田市高齢福祉室から、DVを受けている方の緊急避難措置に関する相談を受け、高寿園のショートステイを利用から特養への入居に至ったケースがあるそうです。
 小川さん: 高齢者の方の場合は、介護保険を利用して特養に入居するという選択肢があります。高齢福祉室からのダイレクトな相談も、今後は増えるのではないかと考えています。
小川さん: 高齢者の方の場合は、介護保険を利用して特養に入居するという選択肢があります。高齢福祉室からのダイレクトな相談も、今後は増えるのではないかと考えています。

居住支援の分野でもソーシャルインクルージョンを目指す高寿園。その取り組みが注目を集め、他の済生会支部も視察に訪れているそうです。
私たちの暮らしに直結する「住まい」の問題。社会、地域全体が抱える課題を解決すべく、「特養」という役割の枠組みを超え、さまざまな参加団体と連携し強みを活かしあう――“居住支援法人 高寿園”の挑戦は続きます。
新着記事