
「認知症マフ」が地域に広げるケアの輪。
拘束に頼らない認知症との付き合い方を考える
超高齢社会で認知症ケアは早急の課題に
日本の人口は減少傾向にある一方で、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は増え続けており、2025年に高齢化率は過去最高の29.4%を記録。2055年には38%台になると推計されています。
高齢になるにしたがって心配事となるのは認知症。75歳を超えると、10%以上の人が認知症を発症するというデータもあります。 「自分が認知症になったらどうしよう」「認知症の家族をどのようにサポートしたらいいか分からない」。そうした漠然とした不安を抱えている人は少なくありません。超高齢社会が進む今、認知症をどのように予防し、発症後にどのように向き合っていくかは、私たちに共通する大きな課題となっています。
東京都墨田区にある東京都済生会向島病院では、2022年に物忘れ・認知症外来が開設されました。診療は毎週土曜日に行なわれ、訪れる人の多くは、普段から別の疾患で向島病院に通院している患者です。例えば、薬の管理ができていない、身なりが整えられていない、予約日に病院に来られない⋯⋯そうした違和感に気づいた看護師などのスタッフが、認知症外来へとつないでいます。

1922年に前身となる東京都済生会寺島出張診療所が開設以降、墨田区に住む人々の健康を見守ってきた向島病院
糖尿病や肺炎、尿路感染症などを患って向島病院に入院する人は、70~80代の高齢者が多く、もともと認知機能が低下しているケースも多くあります。また、とりわけ配慮が必要になるのは入院後のせん妄です。せん妄とは、身体に何らかの負担がかかったことが原因で、突然発生する精神機能の障害です。
入院時には認知機能のスクリーニングを行っており、病棟では専用のチェックリストでせん妄のリスクがあるかなどを確認します。
本人が持っている力を引き出す見守り
松野芳さんは、向島病院に勤務する認知症看護認定看護師です。認知症看護認定看護師とは、認知症に関して熟練した看護技術や知識を持った看護師のことで、専門研修の受講のうえ、日本看護協会による認定審査に合格することで認定を受けることができます。
松野さんがせん妄や認知症の症状が見られる入院患者と接するときには、今日が何月何日か、なぜここにいるかといった患者自身の置かれている状況を尋ねる「見当識(けんとうしき)」の確認を行なっています。毎日、名刺を見せながら自己紹介し、出身地や普段の生活のことを聞くといった声かけも欠かしません。

1998年から向島病院で看護師として勤務し、その後2018年に認知症看護認定看護師の資格を取得した松野さん

認知症看護認定看護師
松野 芳さん
認知症ケアの基本は、患者本人の持っている力を引き出すことです。昼夜の生活リズムをつくれるよう、昼間はなるべく起きてデイケアでレクリエーションをしたり、車椅子に乗れる方でしたら日光を浴びていただくようにしたりしています。リハビリをはじめたら、トイレに行ったり、座ってごはんを食べたり。これまでされていた日常動作や習慣を積み重ねていくことが大切です。
認定看護師として、身体拘束最小化にどう取り組むか
松野さんが認知症看護認定看護師の資格を取るきっかけは、10年以上前の出来事にあると言います。
同じように印象的な出来事として、脳梗塞後、脳血管性の認知症を発症した患者との出会いもありました。入院中にどうしても落ち着きがなくなり、医師と家族の同意のもと、ベッドの足元に介護用のテーブルを固定する形で“身体拘束”を施すことになりました。自分で起き上がってけがをすることを防ぐためです。退院後、自宅に帰ることはできず施設に入所したと聞いた松野さんは、認知症ケアの難しさを実感しました。
松野さん:拘束をしなければならないほど落ち着かない一番の理由は、環境不適応から来る不安感や違和感です。点滴など普段は体に付いていないものがある、なぜ治療しているか分からない、自分の状況が分からない上に体調も辛い。そういった苦しさや痛みにうまく耐えられないという状況の方が多いように思います。
身体拘束をめぐっては、避けるべきであるという大前提に加えて、「切迫性」「非代替性」「一時性」という3原則に照らし合わせ、慎重に実施を判断することが求められています。2024年には、国の医療保険制度に基づく診療報酬改定に合わせ、院内に身体的拘束最小化チームを設置すること、拘束を行なう場合は緊急やむを得ない理由を記録すること、職員教育を実施することなど、身体拘束の最小化に向けた取り組みが強化されました。
向島病院では、病棟にいるスタッフ2人以上で相談し、3原則にいずれも該当する場合のみ、医師へ連絡の上、家族から同意書を受け取って最低限の拘束を行ないます。
松野さん:点滴や酸素のためのチューブを外してしまう方には、手袋型の拘束帯である「ミトン」を付けていただくことがあります。ただ、「外して」と言われることが多く、明らかに嫌がっていらっしゃることが分かります。もう10年以上前ですが、外そうと必死に歯で噛んで、ミトンに血が滲んでいるようなこともありました。治療上やむを得ないことですが、本当に辛いだろうと思いますし、私たちも本当に切ない心情で葛藤を覚えます。
せん妄が次第に落ち着き1日で拘束を解除できる人もいれば、治療上、高濃度の酸素がどうしても必要な場合など、しばらく拘束を続けざるを得ない場合もあるのが現実です。
希望を感じた「認知症マフ」
拘束を減らす方法を模索する松野さんは、2023年6月に行なわれた日本老年看護学会で目にした、とあるグッズに希望を見出しました。イギリスから始まった「Twiddle Muff(トゥィドル・マフ)」です。日本では「認知症マフ」と呼ばれ、介護や医療の現場で活用され始めていました。
毛糸で編まれた筒状の認知症マフは、両側から手を入れてぬくもりを感じたり、内側や外側についた飾りを触ることで安らぎを得たりすることができるアイテムです。

さまざまな色や模様で作られる認知症マフ。内側、外側には毛糸などで作られた飾りが付いていて、目で見て手で触れて、心身の緊張感を和らげることができる
松野さん:手作りということで入手する方法も分からず、すぐには実用に至りませんでしたが、数カ月後、看護部長から「済生会のほかの施設で、認知症マフを活用して身体拘束が外せたという報告があった」と聞き、院内のスタッフに声をかけてみようということになりました。一斉メールで投げかけたところ、編み物が得意なスタッフが数日で試作品を持ってきてくれたんです。
早速、ミトンを使用していた患者に試してもらったところ、ご家族は「拘束が外せる」と大変喜ばれました。ご本人は言葉による意思表示が難しい状態でしたが、ミトンを必死に外そうとしていた時のような拒否反応はなく、穏やかに受け入れているようでした。以降、拘束の代替として認知症マフを活用するようになりました。

認知症マフを使用している患者からは「ふわふわしてあったかい」という声が聞かれた
小さな工夫が大きな変化に
向島病院の場合、患者に認知症マフを渡した後、点滴などの治療器具を外すといったトラブルが起きなくなったケースは全体の6割、拘束を解除できた人まで含めると8割で効果が見られています。もちろん、マフさえあればすべての人が常に落ち着くわけではなく、マフを含め、同時にいくつかの対処を取ってみた結果得られた効果でした。
松野さん:試せることが多いほど、拘束を外せる可能性が上がります。「こうしてみよう」「次はこっちを試してみよう」と試行錯誤できるように、選択肢は複数あった方がいい。マフの使用だけではなく、例えばデイケアの頻度を増やしてみたり、点滴の時間を短くできないか医師と相談してみたりといった工夫も意味のあることだと思います。

暑い夏でも使えるよう、ミシンが得意な病院スタッフが制作した布製の認知症マフ
向島病院で使用している認知症マフは、現在看護師や栄養士、事務スタッフなどの病院職員が手作りしています。感染予防の観点から、患者間での使い回しや退院時の持ち帰りはしないよう決められているため、常に在庫が必要です。しかし、さらに多くの認知症マフを入手したくても、材料費や謝礼等の都合により、病院側から外部の人や団体にマフの制作を頼むことは難しいと松野さんは話します。
そんな中、地域住民が認知症マフの作り手となり、出来上がったマフを近隣病院へ精力的に寄付するなど、認知症ケアのサポート体制を地域へ広げている施設があります。それが、神奈川県横浜市金沢区にある済生会横浜市六浦地域ケアプラザです。
地域住民がマフの作り手に 横浜市六浦地域ケアプラザの取り組み
地域に住む高齢者や障害者などに向けた福祉・介護サービスを提供する六浦地域ケアプラザでは、2022年4月からボランティア部による認知症マフ作りが始まりました。同施設の地域活動・交流コーディネーターとして、地域の福祉保健活動を支援している山田和恵さんの呼びかけによるものです。
2026年現在、50人以上の地域住民がボランティア部に所属し、月1~2回の活動の中で認知症マフが制作されています。施設での活動時間にとどまらず、参加者が自発的に自宅でマフを作ってくることも多いそう。マフ作りに使われる毛糸や布などの多くは地域住民からの寄付のため、材料費はほとんどかかっていません。
マフ作りに参加する人の多くは60~80代。六浦地域ケアプラザが発行する広報紙や、施設を訪れた際の職員からの声かけ、友人からの紹介などが、参加するきっかけとなっています。

参加者の中には元々編み物が趣味の人が多く、和気あいあいと会話を楽しみながら、あっという間にマフが作られていく
ボランティア部の活動メンバーの一人である林征子さんは、認知症マフ作りについて、このように話します。
林 征子さん:ボランティア部は、自分の都合が合う日だけ、また活動時間の途中からでも参加できるため、無理せず続けられています。仲間に会う楽しみも参加を続けている理由のひとつです。ボランティア部でのマフ作りの活動は楽しいだけでなく、人の役に立つことができます。いろいろな人との出会いもあり、この活動を通して私自身も元気をもらっていて、今では生きがいになっています。
ボランティア部で制作された認知症マフは、済生会横浜若草病院や、済生会神奈川県病院など、横浜市内外の5つの病院へ寄贈されています。寄贈先の病院からは、マフの作り手への感謝の言葉とともに、「認知症マフはコミュニケーションツールにもなり、病院内があたたかい雰囲気になる」「もっと欲しい」といった声が寄せられています。

若草病院で実際に使用されている、六浦地域ケアプラザ寄贈の認知症マフ。寄贈先で使用されたマフを修理のため回収した際には、強くにぎられた跡が付いていたものもあったという
また六浦地域ケアプラザは、認知症患者やその家族への見守りの目を増やすため、地域住民を対象に認知症の症状や対応方法などを説明する「認知症サポーター養成講座」を開催しています。横浜市立大道中学校など近隣の小・中学校で、児童生徒やその保護者に向けて講座が行なわれているほか、その他地域の施設や店舗、自治会などからも講座の依頼を受けているそう。

横浜市六浦地域ケアプラザ 地域活動・交流コーディネーター
山田 和恵さん
認知症サポーター養成講座を実施した後には、受講者に認知症マフに取り付ける小さなパーツ作りに挑戦していただくなど、認知症サポーターをさらに増やすための活動を継続的に行なっています。講座や認知症マフ作りを通して子どもも大人も認知症への理解を深め、認知症患者やその家族を含めたあらゆる人が安心して暮らせるまちづくりを推進していけるよう、今後も活動を続けていきます。
地域で支える、これからの認知症ケア
認知症患者の負担を軽減する一つの選択肢として活用され始めている、認知症マフ。さらに横浜市六浦地域ケアプラザでは、認知症マフをきっかけに地域住民による認知症サポートの輪が広がっています。認知症の人やその家族を支える地域のネットワークは、超高齢社会や核家族化が進むこれからの日本において不可欠な存在です。

松野さん:向島病院がある地域は一人暮らしや高齢者世帯も多いエリアなので、退院後自宅に帰るとなると、支える体制や受け皿が必要です。病院や訪問介護などだけでは“点”の支援ですから、ケアマネジャーや薬局など、さまざまな人がつながっていくことが大切だと思います。一人ひとりが頑張るだけではどうにもならないことですから、地域全体で認知症ケアを考えていけるとよいなと思います。
認知症マフ、そして拘束に頼らない認知症ケアのあり方を考えると、病院の中だけでなく、地域の中で支える仕組みをつくる重要性が浮かび上がってきます。マフの活用をはじめとする、認知症のある方の自由や尊厳を守るためのさまざまな工夫や取り組み、そして地域全体で認知症への理解を深めるまちづくりが全国に広がることは、認知症の人やその家族を取り残さない、“認知症とともに生きる”社会実現への大きな一歩となるはずです。
新着記事



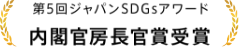















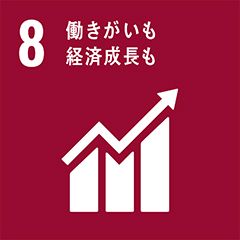







松野さん:肺炎で入院していた患者が、「家に帰りたい!」と怒って病院の外へ出てしまい、やっとの思いで連れ帰ったことがありました。年齢相応の認知機能の低下はあったものの、当時の私には、その方がなぜそうした行動を取られたのか理解できませんでした。そこから、認知症についてちゃんと勉強したいと思うようになりました。