
医療的ケア児を育てる家族も心身健康でいられるために―― 訪問看護師が行なう「在宅レスパイト」とは?
*令和4年厚生労働省「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策(医療的ケア児について)」より
済生会下関総合病院とレスパイトの歩み
山口県下関市。市街地を一望する高台に建つ済生会下関総合病院は、地域がん診療連携拠点病院や二次救急指定病院として、地域医療を支える総合病院です。また、地域周産期母子医療センターの指定を受けていることから、多胎妊娠や胎児の発育不全、若年・高齢出産など、母子共にハイリスクな出産に立ち会う機会も多く、医療的ケアが必要な子どもたちや家族にとっても、最初の相談場所として重要な役割を担っています。

下関診療所を前身として、1959年に済生会下関総合病院として創設。2006年、地域周産期母子医療センターの指定を受ける
日本での医療的ケア児の支援は、2000年代に入り大きく変化しました。それまで病院での生活を余儀なくされていた重度の身体的障害のある子どもが、医療の発展により、自宅でも家族の手によって医療的ケアが受けられるように。一方で、24時間体制での日常生活の介助、大半の医療的ケアを担う家族の負担が一層大きくなりました。
そんな中、下関総合病院では、2010年頃からレスパイトケアの受入れを行なっています。一時的に病院で子どもの医学的管理をしている間、家族の身体的・精神的負担の軽減やリフレッシュなども図ることができるという取り組みです。

小児科科長 小児循環器科科長 小児リハビリテーション科科長
石川 雄一さん
ご家族は子どもが生まれた時から、24時間365日ケアにあたっており、その負担は相当なものです。レスパイトは、ご家族が心身を休め健康を保ちながら、子どもと向き合うために不可欠なケアだと考えています。

医療的ケア児の入院時に使用される病室。下関総合病院の小児科では、医療的ケア児を出生後から成長の過程にわたって、継続的に支援している
入院でのレスパイト、受け入れの難しさ
しかし、現在下関総合病院では、入院でのレスパイトの積極的な受け入れは行なっていません。レスパイトの受け入れを拡大できない背景には、現場の苦悩が見え隠れします。

2002年から19年間にわたり在宅ケア科の看護師として医療的ケア児の支援を担当したのち、2025年より下関総合病院の看護部長を務める首藤悦子さん

看護部長
首藤 悦子さん
私たちの病院の根幹となる役割は、急な病気や事故で運ばれてくる患者さんを助ける“急性期医療”です。そのため、緊急性の高い患者さんの受け入れとレスパイトを両立させることには難しさがあります。また、医療的ケアを必要とするお子さんには専門的なサポートが不可欠なため、他の患者さんへの支援とのバランスも考慮する必要があり、どうしても受け入れには慎重にならざるを得ません。
病床確保や専門スタッフのマンパワー不足などを理由に、入院でのレスパイトは拡大していくのが難しいと首藤さん。そんな中で、下関総合病院が今取り組んでいるのが、訪問看護の仕組みを応用した「在宅レスパイト」です。
注目される「在宅レスパイト」の可能性
在宅レスパイトとは、従来の数日間、医療機関や福祉施設で過ごすレスパイトとは異なり、主に看護師が医療的ケア児の自宅を日中数時間訪問してケアを行ないます。ご家族は、その間に自身の通院や買い物、余暇を楽しむなど、思い思いの時間を過ごすことができます。
下関市では、訪問看護を提供する5つの事業所によってこのサービスが実施されており、下関総合病院では「在宅ケア科」に所属する4人の看護師が在宅レスパイトを担当しています。
ケアの内容は、人工呼吸器の管理や痰の吸引、経管栄養の注入といった医療的ケアが基本ですが、その子の好きな絵本を読んだり、タブレットで一緒に動画を見たりと、家での普段の過ごし方と同じように、自宅での生活全般のケアなども行ないます。

医療的ケア児のご自宅を訪問する在宅ケア科の看護師・栗田麻里菜さん。在宅レスパイト実施時は、初めに家族から当日の過ごし方についてヒアリング。本人ともコミュニケーションを取りながら当日の過ごし方を決めていく
訪問看護師が在宅でレスパイトを行なうことで、病院の病床運用を気にすることなく、医療的ケア児の支援に集中することができます。また、子どもが一番安心できる自宅でケアを受けられるという、本人や家族にとっての利点もあります。

在宅ケア科の看護師長として下関総合病院の在宅レスパイトの現場責任者を務める橋本道子さん。多職種連携の橋渡し役となり、医療的ケア児が適したサービスが受けられるよう調整する医療的ケア児支援コーディネーターの資格も持つ

在宅ケア科 看護師長
橋本道子さん
例えば、在宅レスパイトを利用して、きょうだいの学校行事にご家族が参加できた時は、やり甲斐もひとしおです。医療的ケア児のきょうだいたちは、口には出さないけれど、日常生活のどこかで我慢をしてしまっていることがあります。授業参観なども、レスパイトがなかった頃は、「ごめんね、お母さんは行けないから……」と諦めるしかなかったと聞きました。在宅レスパイトを利用することで、「家族が自分のためだけに学校に来てくれた!」という経験をさせてあげられる。医療的ケア児本人だけでなく、ご家族みんなを元気にする大切な支援だと、改めて実感します。
しかし、重要な目的の一つである家族の「リフレッシュ」のためのレスパイト利用とは、まだまだ距離があるといいます。

下関総合病院の訪問看護の利用者は約40人、そのうち約3分の1が小児。「医療的ケア児のレスパイトの場合、お子さんと2人きりになる時間が多く責任も大きいので、毎回気が引き締まります」(看護師・栗田さん)
下関市の「在宅レスパイト事業」で経済的負担を軽減
下関市は、山口県内でも人口が最も多く、2022年の調査では医療的ケア児の数も52人と県内で最多。これまで市内で行なわれる医療的ケア児の支援については、障害児・障害者全体を対象とした「自立支援協議会」の中で議論されていましたが、市内の小児科医を中心とする担当者からの強い要望もあり、2019年2月に「医療的ケア児支援地域連携会議」が設置されました。
この会議は、医療的ケア児に関する支援施策や意見を共有し、関係機関が連携することを目的として、年2回開催されています。会議には、済生会下関総合病院の新生児科医や市中の小児科医をはじめ、山口県看護協会下関支部や山口県訪問看護ステーション協議会下関支部の代表者、地域の福祉・保育・教育の現場で働く関係者、そして実際に医療的ケア児を育てる家族の代表者が参加しています。
会議の中で、他の自治体でのレスパイト事例の共有に加え、「24時間ケアによる負担」や「きょうだいの行事に参加できない」といった家族からの具体的な悩みが挙げられたこと、さらには、2021年の「医療的ケア児支援法」の施行を受け、2024年からは下関市独自の「下関市医療的ケア児在宅レスパイト事業」がスタート。
この事業は、医療的ケア児の家族が在宅レスパイトを利用する際にかかる費用を、市が負担するもので、医療的ケア児の家族が利用している訪問看護事業所を通じて市に申請すれば、在宅レスパイトを自己負担なしで利用することができます。利用時間は年間48時間で、1回ごとの上限はありません。
医療的ケア児にかかわる法整備をきっかけに、行政が経済的に支援することで、「在宅レスパイト」をより利用しやすくすることが狙いです。

下関市障害者支援課の濵﨑俊一課長(右)と宮﨑覚大(左)さん。幼児保育課や学校教育課が協働し、医療的ケア児を保育施設や小中学校が受け入れるためのマニュアル作成など、医療的ケア児が他の子どもたちと一緒に生活できるような試みも進行中

下関市 障害者福祉課 課長
濵﨑 俊一さん
この7月で「医療的ケア児在宅レスパイト事業」がスタートしてから1年が経過し、市内で訪問看護を利用している医療的ケア児のおよそ25%にあたる12人の方が登録されています。現状では、年間の利用上限48時間をフルで利用している方はいらっしゃいませんので、今後は利用者であるご家族や関係者からの意見を広く集め、制度の周知や利用の促進を強化していきたいと思います。
地域全体で子どもたちを支える未来をつくる
済生会下関総合病院がある下関市では、東西に約30km、南北に約50kmと、市街地から山間エリアまで広域にわたって訪問看護サービスを提供しています。圏域のさまざまなエリアに医療的ケア児が居住する中で、下関総合病院だけで在宅レスパイトを運営していくのは難しいと、首藤看護部長。この課題の対応策として、「地域の受け皿を増やしていきたい」と語ります。

首藤さん:下関エリアは広く、下関総合病院だけで全域をカバーすることは難しいと感じています。医療的ケア児に対応できる訪問看護ステーションを増やし、何かあったときにすぐに駆け付けられるような体制をつくることが大切です。「小児は専門外だから……」と不安がる事業所も多いのですが、例えば、週3回の訪問のうち、当院が1回、残りの2回を患者さんのご自宅に一番近い地域の訪問看護ステーションにお願いするなどで、協力、連携し、医療的ケア児に対応できる訪問看護ステーションを徐々に増やしてきました。今では圏域に7事業所と連携。今後はもっと連携できる事業所をより増やしていきたいと考えています。
さらに、地域で暮らす人々が医療的ケア児への支援について理解を深め、レスパイトなどのサービスや制度を家族がより利用しやすくするためには、「医療的ケア児がほかの子どもたちと同じように保育所や学校に通える環境づくりも大切だ」と、橋本師長は話します。

橋本さん:医療的ケア児支援の最終的なゴールは、保育所や学校など地域社会へ、出ていきたい時に、出ていけるような環境を整えることだと思います。医療的ケアが必要な子どもは普通学級での生活は難しいと思われることも多いですが、医療的ケアさえ受けることができれば、普通学級に通える子どももいます。医療的ケア児が社会参加する機会が増えることで、その存在や生活状況をより身近に認識できるようになります。そうして、彼ら、彼女らを支える家族が24時間体制でケアにあたっていることや、その家族が休息を取る時間がいかに重要であるかという現実的な課題への関心も高まるのではないでしょうか。

屋上や病棟の窓からは下関市街地や関門海峡を航行する貿易船、海の向こうには九州を望む
新着記事



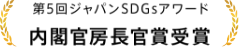
















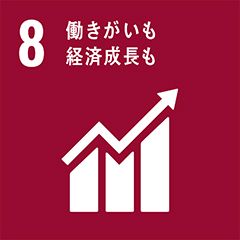






橋本さん:現在、レスパイトの利用目的のほとんどは、きょうだいの学校行事やご家族の通院の際の一時預かりです。夫婦でたまの食事に行ったり、もっと言えば、医療的ケアが必要な子どもを連れての外出に看護師が同行する時なども、在宅レスパイトとして利用することは可能なのですが、ご家族の遠慮もあり、そういった利用はこれまで行なったことがありません。今後、レスパイトについての理解が社会全体に広がることでより制度を利用しやすくなることに期待したいですね。