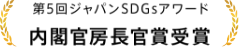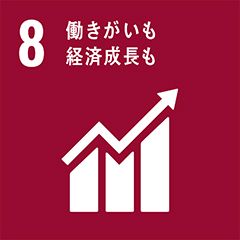みんなで地域の魅力を創造。
就労支援から生まれた小樽みやげ「おたる水族缶」
医療・福祉にとどまらない北海道済生会
北海道済生会は、明治時代から北海道有数の港町として発展を遂げ、現在は観光地としても親しまれる「小樽」を拠点に、済生会小樽病院や小樽老人保健施設 はまなす、重症心身障がい児(者)施設みどりの里などの、医療・福祉施設を展開。2024年7月に創設100周年を迎えました。
2020年からは、「ウエルネスタウン構想」を掲げ、行政や地元企業らと協同しながら、地域に暮らすすべての人々が「100年暮らしたい」と思えるまちづくりを進めてきました。
2023年には、小樽市と「地域共生社会の実現に関する包括協定」を締結。小樽市との協働で生まれた、大型商業施設内に開設した市民のための健康福祉ゾーン「済生会ビレッジ」では、生活困窮者支援やフードバンク、子どもの発達支援、地域の交流イベントなど多岐にわたる事業を展開し、オープンからわずか4年で年間約3万人が利用する場へと成長しました。
他にも、住民参加型農園「そらし〜ど」の運営や、発達⽀援事業所きっずてらすの子どもたちが描いた絵や文字を“フォント”として販売する「小樽フォント」など、医療・福祉の枠にとどまらない、まちぐるみの活動を展開してきました。
「福祉」と「地域活性化」を同時にかなえる、小樽発の挑戦
このような包括的な活動の一環として生まれたのが、就労継続⽀援事業所ぷりもぱっそ(B型)と地元企業が共同開発した新しいお土産、「おたる水族缶」。小樽市の観光名所「おたる水族館」の生き物たちをモチーフにした、手のひらサイズのフィギュアが詰まったユニークな商品です。

現在、おたる水族館のアイドル「フンボルトペンギン」をモチーフにした「ペンギン缶(左)」をはじめ、「トド缶(右)」「フウセンウオ缶」「アザラシ缶」「食べられる魚缶」の5種類を展開。今後は、真っ白な魚に自分好みの色を塗って楽しめる「おたる水族缶~ぬりぬりクラフト版~」などの開発も検討中
この商品の最大の特徴は、フィギュアの製造や缶詰の作業工程の一部を、障害者の就労を支援する就労継続支援事業所ぷりもぱっそで担っていること。ぷりもぱっその利用者が地域の方やお土産を買う観光客をつなぐツールにもなっています。また、おたる水族缶の利益は利用者の工賃に還元されます。
プロジェクトの背景には、福祉事業が補助金なしでは成り立たない現状への強い問題意識があります。北海道済生会が運営するぷりもぱっそは、道内の平均工賃(約300円/時間)を大幅に上回る580円/時間を実現していますが、それでも事業の継続には補助金が不可欠です。
「福祉が補助金に頼る状態から脱却し、事業として自立できる仕組みを構築したい」と語るのは、北海道済生会で本活動を統括する櫛引久丸常務理事。障害者の経済的自立を支援するだけでなく、将来的には「ソーシャルファーム」として事業化し、持続可能な雇用を生み出すための大きな一歩になるといいます。
“チーム小樽”結成! 「おたる水族缶」商品開発の裏側
商品開発は、このような北海道済生会の熱い想いを小樽市に伝える形で地元企業に声掛け。この構想に共感し、障害者への支援と地域のお土産づくりを掛け合わせたプロジェクトが本格的に動き出しました。
協力したのは、海の生き物の魅力的な展示で人気の「おたる水族館」、老舗缶メーカーの「北海製罐株式会社」、そして商品企画やデザインを得意とする地元企業の「株式会社エムブイピークリエイティブジャパン」です。

初回の打ち合わせでは「商品コンセプトをはじめ、水族缶商品の中身、フィギュアを製造するためのデータの作成方法」などについて話し合われた
最初の難関は、フィギュアの原型づくりでした。
当初、スーパーで買ってきた魚をスキャンする案も出ましたが、おたる水族館の古賀崇総務次長は、「死んだ魚をスキャンしても、死んだ魚のフィギュアにしかなりません」と指摘。生き物本来の躍動感や魅力を表現するためには、生きた姿からデータを取る必要があると提言したのです。
結果として、生き物に精通した獣医の角川雅俊氏が協力し、「おたる水族館」の生き物たちの魅力を最大限に引き出すための3Dデータを作成。3Dプリンターでの開発を得意とする「エムブイピークリエイティブジャパン」が、そのデータを基に精巧なフィギュアを形にしました。

プロジェクトに参加したおたる水族館の伊勢伸哉館長(左)、角川雅俊獣医(中央)、本間宏信常務理事(右)
さらに、フィギュアを詰める缶についても、安全と使いやすさを追求しました。「北海製罐」は、子どもたちが安全に楽しめるよう、大小さまざまな種類の缶の中から、縁が丸く加工されたものを提案。また、就労継続支援事業所の利用者でも簡単に封ができるよう、手動式の「ハンドシーマー」方式が採用されました。

ハンドシーマーは、缶詰の封をするための機械の一種で、缶本体と蓋を巻き込んで密閉する「巻締(まきしめ)」という工程を行う装置。手動式のものは、ハンドルを回すだけで簡単に封をすることができ、誰でも比較的簡単に缶詰が可能
こうして、細部にわたる配慮を重ねることで、高品質でありながら、障害のある人でも製造に関われる仕組みが実現したのです。このプロジェクトは、単なる商品開発ではなく、地域のあらゆる人々の知恵と想いが詰まった、まさに“チーム小樽”としての取り組みに変貌していきました。
地域を巻き込む「水族缶」体験型イベントも
「おたる水族缶」は、2024年12月のリリース後、読売新聞や地元ラジオ、テレビ局でも取り上げられ、「北海道お土産グランプリNorth Wave Selection2025-2026」で金賞を受賞。小樽市のふるさと納税返礼品に採用されるなど、地域全体から大きな注目を集めています。現在、おたる水族館をはじめ、小樽駅、札幌駅の土産物店など道内5か所とオンラインサイト「ぷりもショップ」にて販売されています。
また、さらに多くの人に商品に触れてもらおうと、「水族缶づくりワークショップ」の事業化も計画中です。参加者がフィギュアに色を塗り、缶に詰めて持ち帰るこの体験型イベントは、すでに市内でも開催され、幼稚園などでも実施されています。

北海道済生会主催の「済生会小樽くらしたい共生フェス2024」で行なわれた「水族缶づくりワークショップ」。当日は182人が参加した
開発を担当した北海道済生会ソーシャルインクルージョン推進室の土谷浩大さんは、「この商品は、小樽で暮らすさまざまな人たちの想いが込められています。一人でも多くの方にこの魅力をお届けし、地域全体を巻き込んだ活動につなげていきたい」と今後の展望を語ります。
この取り組みは、地域企業や行政との強固な連携を生み出し、障害者支援と地域のお土産づくりを結びつけた画期的な試みです。それはまさに、誰もが参加できる社会を目指す「ソーシャルインクルージョン」の理念を、具体的なまちづくりとして形にしたモデルケースと言えるでしょう。

開発に関わったメンバー。「おたる水族缶」事業は、単なるお土産づくりにとどまらず、地域企業や行政との関係構築にも大きく貢献。今後、他の活動でも連携が期待されます
新着記事