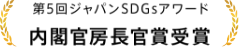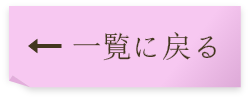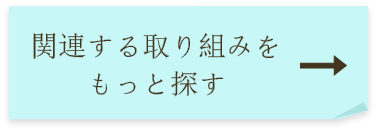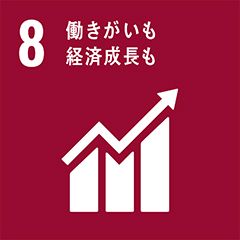【意思疎通支援】
いしそつうしえん
障害をもつ人が、周囲の人と考えや認識を共有し、理解し合う「意思疎通」を日常生活で図ることができるよう地方自治体が実施する支援事業のこと。厚生労働省が障害者総合支援法の中で各地方自治体の必須事業として定めています。聴覚や視覚、失語、知的障害といったさまざまな障害、また難病のために意思疎通を図ることに支障がある人が対象です。例えば、通院、余暇、買い物など、地域での日常生活を送る上で意思疎通が障壁となる場合、手話通訳者や点字奉仕者など、それぞれの障害特性にあわせた意思疎通支援者を地方自治体が派遣します。また、事業の中ではこうした支援の担い手が不足しないよう、国が、国立障害者リハビリテーションセンターや社会福祉法人に委託して指導者を育成し、都道府県と市区町村に手話通訳者などの養成を義務づけています。こうした意思疎通支援は合理的配慮を提供する方法のひとつになります。
参考サイト
意思疎通支援(厚生労働省)
事例