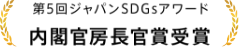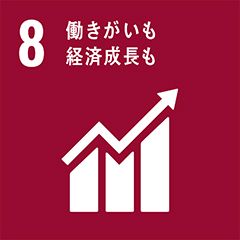「8050問題」「ひきこもり」
“見えない”存在の声を聴く、アウトリーチ支援の現場から
埼玉県済生会鴻巣医療福祉センター アウトリーチ支援チーム
現在、国内で精神障害や精神疾患を持つ人の外来通院は増加傾向にあり、2022年(令和4年)の障害者白書によると約 419万人、実に国民の約30人に1人の割合に上ります。通院していない人を含めると、さらにその数は増えると予測されますが、「身近にいない」ように感じるのは、実は多くの場合がSOSを発せず、地域との接点を失ってしまっているからかもしれません。そんな“見えない”存在に手を伸ばし、地域へとつなぐアウトリーチ支援について取材しました。
「アウトリーチ」はなぜ必要?
アウトリーチとは、必要としている人に必要なサービスを届けること。
特に社会福祉の分野では、必要な助けが届いていない人に対し、行政や支援機関が訪問支援などでアプローチを行なうプロセスのことを指します。
厚生労働省は、精神障害を持つ人の地域生活を包括的に支援するシステムとして、「精神障害者にも対応した地域包括ケア構築推進事業」のメニューにアウトリーチ支援事業を位置づけました。中でも埼玉県は、全国でもいち早くアウトリーチ支援事業を推進する計画を策定。2018年から済生会鴻巣病院がそのモデル事業を引き受け、実施しています。
2021年には社会福祉法の一部改正に伴い基礎自治体による「重層的相談支援体制整備事業」においてもアウトリーチ等を通じた継続的支援事業が位置づけられています。さまざまな社会変化の中で、地域や家族から孤立し困窮した方への“支援力”を地域のみんなでどう作っていくかが各市町村で今、大きな課題となっています。
鴻巣病院のアウトリーチ支援チームで代表を務める病医院事業本部 支援部長の関口暁雄さんは、地域の中でのアウトリーチの重要性についてこう話します。
関口さん:精神障害や精神疾患を抱える人は、病気の症状等が原因で外との交流が断絶し、自分からは助けを求めづらいという傾向があります。だからこそ対象となる人の自宅をこちら側が訪ね、時間をかけて関係性を構築しながら、その人にとって“本当に必要な支援”につなぐアウトリーチ支援が必要なのです。

鴻巣病院は、精神科急性期や認知症治療、精神科療養の機能別病棟などを備えた済生会唯一の精神科単科病院。結核病床をもつ分院をルーツに、67年前に精神科病床を併設しました。
当時、精神疾患での長期入院は“珍しくない”ことだったと語る関口さん。しかし時代とともに、必要なサービスを受けながら自分らしく生活する“地域移行”が重視されるようになっていきました。
同院ではそういった時代背景やニーズを汲み取り、病院を母体とした「済生会鴻巣医療福祉センター」 として、2023年現在、精神疾患を持つ人の地域生活をさまざまな側面から支える7施設を展開しています。
関口さん:私たちが目指すのは「地域のための精神病院」。 精神疾患を持つ人の地域生活を支えるため、退院後に身体機能を回復させるための老健やグループホーム、精神障害をもつ人の訓練施設、訪問看護ステーションと、さまざまな施設をつくっていきました。2018年には年々増加する軽症うつや働く人のメンタルヘルスなどを専門にしたサテライトクリニックを開院しています。

連携で地域の“孤立”を見つけ出す
治療後の受け皿として多様な施設をつくったことで間口が広がり、地域との連携が広がったと同時にアウトリーチでしかサポートできない潜在的な患者さんがまだまだたくさんいると気づいたと関口さん。
関口さん:介護のためにケアマネジャーや地域包括支援センターのスタッフが、自宅を訪れて初めて家庭内の問題に気付く、もしくは「実は子どもがずっと外に出られていない」と告げられて発見に至る、いわゆる「8050問題」といわれるケースが増えています。そういったケースの増加を受け、アウトリーチ支援チームがケアマネジャーや介護に携わる専門職のケースカンファレンス(介護保険サービスの会議)に参加することもあります。
介護分野からだけでなく、チームのもとには行政をはじめ、保健センター、警察署、学校、民生委員など、さまざまなところから個別に相談が入ります。
一つひとつの問題に応じて各機関が連携し、対応策を検討するため「アウトリーチ支援に決まったプロセスはない」と関口さん。8050問題に限らず、家族やその周辺人物との関係性も含めた包括的なサポートが重要だと訴えます。
関口さん:経済的な困窮や介護の問題はもちろんですが、「ひきこもり」の問題が難しいのは、DV、無関心、過干渉など、さまざまな家族問題の蓄積の上に起こっていることです。本当に本人が安心できる環境をつくるためには本人だけでなく、家族ともやり取りを重ね、家族関係からほぐしていくことが必要です。
家族関係はもちろん、情報を集め、その人に少しでも結び付く存在を集めていくと、その中の誰かが解決の糸口になるようなことも多いと関口さん。大切なのは、その人の周辺に「小さな輪」をたくさんつくっていくことなのだと言います。
家族単位でゆるく・長くつながる
「家族」全員と、ゆるく長いかかわりを続けていくことを心掛けていると話すのは、チームの一員として直接現場を訪ねる精神保健福祉士の栗田早苗さん。
他機関などから依頼を受けた場合に、まず初めに家を訪問し、病気なのかわからないときは医師に、コミュニケーションで良い方向に向かうかもしれないと判断すればピアスタッフになどと、連携を取りながら必要な対応を判断します。
栗田さん:アウトリーチをしていく中で、本人は困っていなくて、家族や地域の人が心配しているというケースをこれまでたくさん経験しました。ひきこもりの人がいる家は、家族機能が低下していることが多く、そのため家族全体をチームでサポートします。支援に終わりはありません。関係が途切れると、その人たちは誰ともつながらなくなってしまう可能性があるからです。私たちがその人たちにとって“ふと思い出してくれる存在”となり、ゆるく、長く関わりを続けていくことを目指しています。

ピアスタッフだからできること
ピアスタッフとしてアウトリーチ支援に関わる高橋哲さん。“仲間”を意味する「ピア」の名称の通り、自分の体験を活かして何かできないかと考え、生活支援センター「夢の実」の開設の際、縁あって職員として加わりました。
髙橋さん:急に知らない大人が来て連れ出される恐さが私にはとてもわかるし、同じ悩みも多いので本人と距離が近くなりやすいと思います。でも、それはあくまで“近い”というだけで、“同じ”ではないんです。だからこそ安易な共感や簡単に「大丈夫だよ」という言葉を言わないようにいつも肝に銘じています。友達でも支援者でもなく、「困ったときに相談できる距離感にいる人」というのがわたしのスタンス。今ひきこもっている皆に関わるうちに、わたし自身のことも認められるようになったし、前向きに生きることができるようにもなってきました。
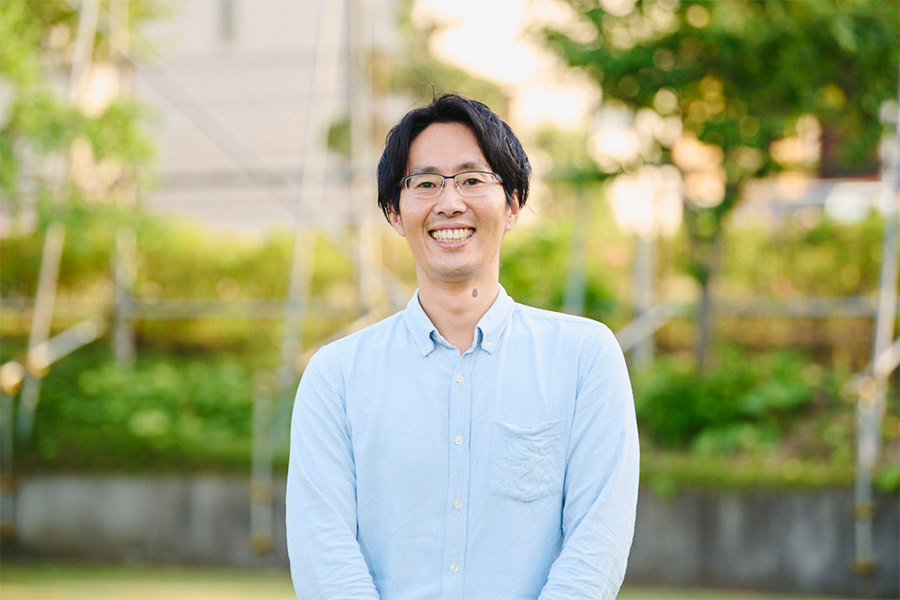
支援した人や家族に少しずつ笑顔が見られるようになると、「よかった」と思うと同時に、関われた人は「ごく一部だと感じる」と話す支援チームの皆さん。
アウトリーチで社会問題にどう取り組んでいけるのか、 社会とつながれない人の声をどうキャッチできるのか、自分でSOSが出せる社会はどうしたら作っていけるのか――常に自問自答しながら、少しでも輪を広げるための地域の場づくりや発信を続けています。
「ひたすら待つ」ことも支援
同院のアウトリーチ支援を後押しするのは、「なでしこメンタルクリニック」院長で精神科医の白石弘巳さん。「杉並家族の会」の勉強会講師など、ひきこもりの家族支援を精力的に行なうほか、支援チームと連携し、医師として自らが現場へ出向くこともあります。
白石さん:アウトリーチ支援は、会おうとしても会えない人に対して、人と交わるきっかけをつくりにいくもの。医師による治療や専門機関につなげばいいということではなく、あくまでプロセスの一つです。本人が治療の必要性を感じていない場合は、専門家が無理に介入することで状況が悪化してしまうこともあります。まずは、その人が関わってもいいと思える状態になるまで、“時が熟する”のを待つこと。「今のあなたのままでいいけど、困っていることがあるならサポートするよ」と肯定することがはじめの一歩です。

子どもがひきこもりになってしまったとき、それが原因となって家庭内の関係がこじれてしまうと、さらにひきこもり状態が長引き、やがて8050問題へとつながっていくことも少なくありません。そうした課題を前に、白石さんが活路と感じていることがあります。
白石さん:関口さんの話にもあったように、介護保険のサービスで家を訪問して、子どものひきこもり状態に気が付くことは多いです。ならばそのような状態を見つけた人が「ゲートキーパー」となり、本人の話を聞き、受け止め、必要なサービスにつなぐことで、より多くの人へ支援できるのではと考えています。
例えば、家を訪問するという行為は、ケアマネジャーにしかできないケースが多々あります。短い時間でも定期的に顔を合わせていれば、関係性を築きやすいという利点がある。孤立に気がついた誰もが支援できるようになるために、さまざまな専門職が関係を築く技術や技法を身につけることで、さらにいい連携が生まれていくように思います。
「見守ること」自体が支援。医療や自立が第三者的に見て必要でも、本人が望んでいることを否定しては、支援していることにならない――「need(必要)ではなく、まずwish(願望)から入ることを大切にしています」と白石さん。
孤立してしまった人の“声なき声”を聴き、その人に本当に必要な支援とは何かを問い続ける「アウトリーチ支援」。 「たった一言の挨拶で孤立が解消することもある」と白石さんが語るように、専門家や機関で役割を区切るのではなく、“誰も”が地域の一員としてお互いを見守り合うこと、そしてそういった地域の輪を少しずつ広げていくことがインクルーシブ社会の実現につながっていきます。
新着記事