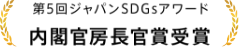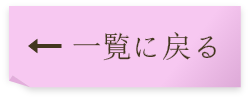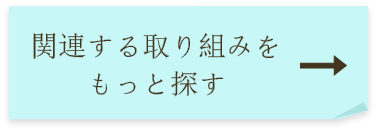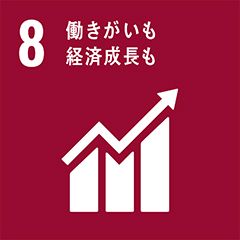【地域共生社会】
ちいききょうせいしゃかい
制度や分野ごとの縦割り、支え手・受け手という関係、世代や分野を超え、それぞれが自分ごととして地域づくりに参画することで、誰一人取り残されず、一人ひとりの暮らしと生きがいがつくられていく社会のこと。人口減少や家族・地域社会の変化に伴い支援ニーズが複雑化する中で誰もが支え合う社会を実現するため、これからの福祉のあり方として厚生労働省が推進している考え方で、2016年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」の中で明記されました。2021年からは、包括的な支援体制を整備するために、障害や子どもといった属性や世代を超えて相談を受け止め、支援を行なう重層的支援体制整備事業がスタートしました。課題を抱えた人を専門的な知識やスキルを持つ支援者・支援機関に橋渡しする相談支援、地域へとつなぐ参加支援、地域にある活動同士をつなぐ地域づくりに向けた支援という3つの支援を一体的に実施することを目指すものです。また、厚生労働省は各自治体に対し、地域共生社会の実現に向けて地域福祉計画の持つ意義を示し、策定・改定を推進するガイドブックを発信しています。
参考サイト
地域共生社会のポータルサイト(厚生労働省)
「地域共生社会」の実現に向けて(厚生労働省)
地域共生社会の実現に向けた地域福祉計画の策定・改定ガイドブック(社会福祉法人全国社会福祉協議会)
関連用語
事例