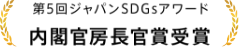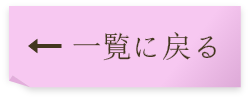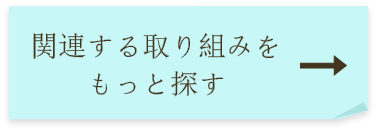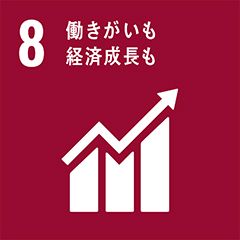【ウェルビーイング(Well-being)】
うぇるびーいんぐ
身体的、精神的、社会的に満たされた状態のこと。満足度、地域幸福度などと訳される場合もあります。定義のはじまりといえるのは1948年に発効されたWHO憲章の前文で、「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあること」と書かれています。日本では、2010年代後半に入ってから国の報告書や調査などで盛んに使われはじめました。2019年には、国内のウェルビーイングの動向を把握するため、内閣府が「満足度・生活の質に関する調査」を開始。医療・福祉分野では、病気を治療するだけではない包括的な支援のあり方を考えるための概念として活用されています。
参考サイト
健康の定義(公益社団法人日本WHO協会)
満足度・生活の質に関する調査(内閣府)
地域幸福度(Well-Being)(デジタル庁)
幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン (はじめの100か月の育ちビジョン)(こども家庭庁)
関連用語
事例
-
こどもの発達を地域で支える
 児童発達支援センターがつなぐ
児童発達支援センターがつなぐ
こどもたちのための“地域連携”とは? 詳細を見る -
観光、福祉、産業が連携し、新たな地域ブランドが誕生!
 みんなで地域の魅力を創造。
みんなで地域の魅力を創造。
就労支援から生まれた小樽みやげ「おたる水族缶」 詳細を見る -
24時間体制で医療的ケア児を育てる家族に休息を
 医療的ケア児を育てる家族も心身健康でいられるために―― 訪問看護師が行なう「在宅レスパイト」とは?
詳細を見る
医療的ケア児を育てる家族も心身健康でいられるために―― 訪問看護師が行なう「在宅レスパイト」とは?
詳細を見る
-
障害者福祉と地域社会をクリエイティブでつなぐ
 福祉施設と地域をクリエイティブでつなぎ、“共創”をデザインするシブヤフォント
詳細を見る
福祉施設と地域をクリエイティブでつなぎ、“共創”をデザインするシブヤフォント
詳細を見る
-
“その人らしい”最期を支える、特養淡海荘の看取りケア
 特別養護老人ホームである淡海荘が
特別養護老人ホームである淡海荘が
ショートステイでも、在宅でも、“看取り”ができる理由 詳細を見る